
農産物直売所と西武黄金時代
唐崎卓也(流通経済大学教授)
私は野球を愛してやまない。小学生時代から50年来の巨人ファンである。巨人ファンではあるが野球全般が好きだ。例えば、野球に関わる技術論、組織論、ひいては人間模様も私の関心の対象である。
「プロ野球史上、いつの時代のどのチームが最強か?」。野球好きの酒飲みならば、朝まで飲みながら話せる永久不滅のテーマだ。私は巨人が9連覇で日本一になった時代をリアルタイムでみていない。それ以降の時代の話であることを断らねばならない。私が思うに、プロ野球史上の最強チームは、西武ライオンズの1980年代から、1990年代前半にかけての「西武黄金時代」と呼ばれた頃のチームではないか。残念ながら我が巨人軍ではない。西武黄金時代のなかでも後期のメンバーがすごい。辻、平野、秋山、清原、デストラーデ、石毛、田辺、伊東と、打撃陣は大技、小技を自在に繰り出し、工藤、東尾、郭、渡辺らの強力な投手陣を擁して守りも堅い。
この時代は、セ・リーグの優勝チームである巨人が、パ・リーグ優勝チームの西武と日本シリーズで何回か激突した。巨人に感情移入している私からすると、西武ほど手ごわい相手はなかった。1983~1990年の間に3回の対戦があったが、いずれも西武が制している。日本シリーズで巨人が何度も力負けするのをみるたびに、悔しさを通り越して、虚無感に苛まれた。
なかでも、1987年日本シリーズでのワンシーンは象徴的である。第6戦の試合終盤の勝負どころの西武の攻撃で、秋山がセンター前にヒット。巨人のセンターを守るクロマティの緩慢な打球処理の間に、1塁ランナーの辻が一気にホームイン。今でもテレビ番組によく取り上げられている例のシーンである。当時、西武の3塁コーチを務めていた伊原コーチは、対戦相手を分析するなかで、クロマティが、ボールを捕球したあとに緩慢な送球をすることを察知していたという。日本シリーズの勝敗の行方を左右するような場面で、その分析を生かす機会がおとずれ、普段からクロマティの緩慢なプレーに対する注意を怠っていた巨人をまんまと出し抜いたわけである。
そろそろ本題の農産物直売所の話に入ろう。私が直売所の研究に携わったときに感じたことなのだが、元気な直売所は西武黄金時代と似ている。私は野球を愛するがゆえの性で、ものごとを「これが野球であれば」と対比的に考える悪い癖がある。当然、直売所の調査をしながら、「もし直売所が野球であれば」など、ふつふつと考えていた。もっと研究に集中しろと言われるかもしれないが、こればかりは性なのでどうにもならない。
直売所にとって生産者は選手である。店舗管理者である店長は監督、店員はコーチだ。元気な直売所は、強い野球チームと同じで、ひとことでいえば多様な人材がそれぞれの役割で機能している。それがまさに西武黄金時代と似ているのである。
消費者は直売所に何を求めているのか。どのような調査でも、「鮮度の良さ」と「価格の安さ」の2つの評価要素が突出して高い。しかし、それは消費者が求める直売所への期待としては、もはや当たり前のことといえる。野球でいえば、打撃、投球、守備の基本がプロとして高いレベルにあるということと同じである。直売所にとっての勝負の分かれ目は、品揃えである。しかも地元産の魅力ある商品が豊富にあれば、なおさら強い。品揃えを野球に例えると、連携プレーや打線のつながりといった、チームワークや、監督の采配に該当する。
では、直売所にとって品揃えを充実させるために何が一番重要なのか。それは、様々な得意分野(品目)をもった多様な生産者がいることである。まず、安定した出荷量を誇り、売り場の棚を埋めてくれる経営規模の大きい専業農家の存在は貴重である。野球でいえば、打順の3、4、5番のクリーンナップを担う中軸打者である。例えば、直売所の売れ筋野菜であるトマトの施設園芸農家は、比較的長い期間での出荷が可能だ。しかも売り場の棚に彩りとボリュームを与えてくれる。いわば、花形選手としてファンからの人気を集め、チームの4番を務めるホームランバッターである(近年の野球では2番最強説もあるが)。
しかし、経営規模の大きい中軸農家の多くは、少ない品目に特化しているため、中軸農家ばかりでは、品揃えを充実させることが難しい。多くの直売所では、経営規模は小さいながらも様々な品目に取り組む、少量多品目型の生産者がいることで、直売所全体として品揃えを確保している。そこでは高齢者や女性が活躍している。直売所の魅力を演出する珍しい野菜、その地域ならではの手作り加工品などは、そうした方々が支えている。野球でいえば、多様な特技をもったバイプレイヤーともいうべき選手たちである。長打力はなくとも、バントや進塁打、走塁に長け、チームの勝利に貢献する選手がいるチームが強いのと同じである。
西武黄金時代でいえば、バイプレイヤーには辻、平野、田辺らが該当する。ホームランや打率の数字ではそれほど目立たないが、クリーンナップの強打者の前や後の打順で、チームの勝利に貢献する実によい働きをする。前述の1987年日本シリーズでのワンシーンでは、1塁から本塁まで一気に駆け抜けて、ホームベース上でガッツボーズする辻が、打者の秋山よりもクローズアップされている。まさに、バイプレイヤーが主役に躍り出たシーンともいえる。
さらに西武黄金時代の強さは、中軸打者が異なる個性を発揮し、チームとして機能していたことにもある。同じホームランバッターでも足が速いとか、チームバッティングに長けているといった異なる個性があれば、それを組み合わせて攻撃のバリエーションも広がる。西武黄金時代の秋山は、ホームランバッターだが、ホームラン王と盗塁王の両方を史上初めて獲得したほどの俊足である。出塁すると相手チームの神経を消耗させ、塁をかき回す。同じくホームランバッターの清原は、単なるホームラン狙いのバッターではなく、状況に応じたチームバッティングにも長けている。
直売所でも異なる得意品目をもった複数の中軸農家が、売れ筋の野菜をバランスよく出荷できると、さらに強さを増す。例えば、茨城県つくば市の直売所「みずほの村市場」は、中軸農家が集まり、それぞれが得意とする数品目を定めている。それらを高品質かつ安定的に出荷することで、全体の品揃えを確保し、顧客から支持されている。
最後に、我が巨人軍についても触れておかねばならない。実は、巨人には「史上最強打線」と呼ばれた年がある。それは2004年のオーダーである。打線は、仁志、清水、ローズ、高橋由伸、小久保、ペタジーニ、阿部、二岡、そして清原、江藤、元木と、スターティングメンバーにはおさまらないくらいの強打者揃いである。この年には、実際に年間ホームラン数259本という、とんでもない日本記録をつくった。現在でもこの記録は破られていない。
しかし、チームのシーズン成績は、なんと3位に沈んだ。この年は、ホームラン攻勢による大勝と、一点差による惜敗を繰り返した。そもそも野球は相手よりも1点多くとれば勝ちのスポーツである。勝負どころで1点を取れるかどうかが重要なのだが、この年の巨人にはバントや盗塁、チームバッティングを絡めて1点を取りに行く野球ができなかった。結果的に脆さを露呈し、悲しくなるほど弱かった。
多様性を失ったチームや組織は弱い。それは直売所にも同じことがいえる。西武黄金時代のような、多様な個性をもった選手(生産者)がいるチーム(直売所)こそが強い。
コメント ( 0 )
トラックバックは利用できません。
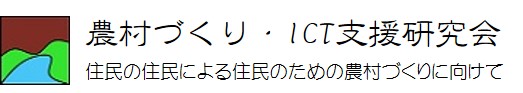









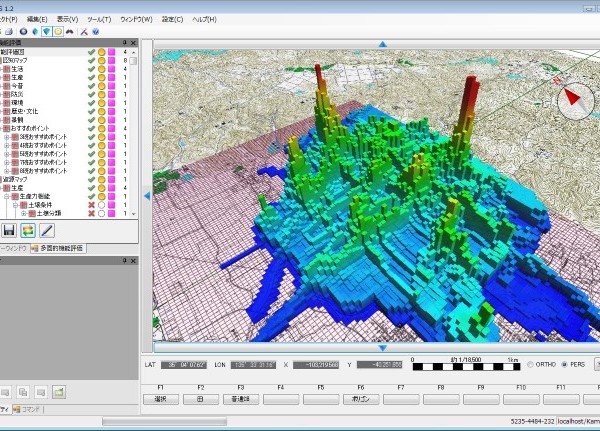










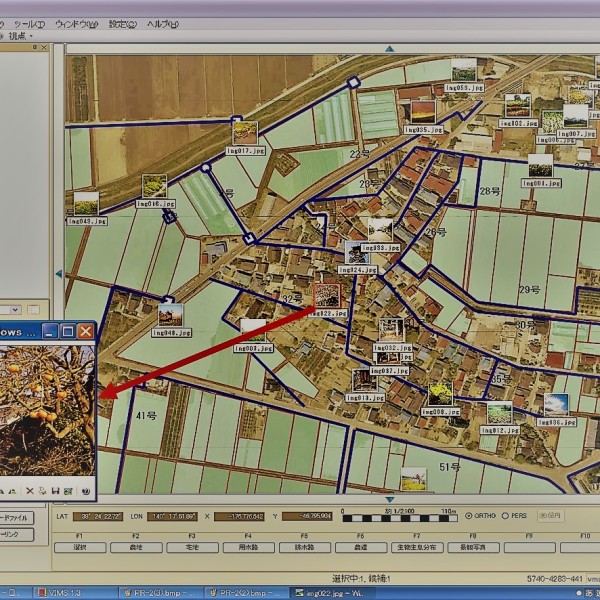
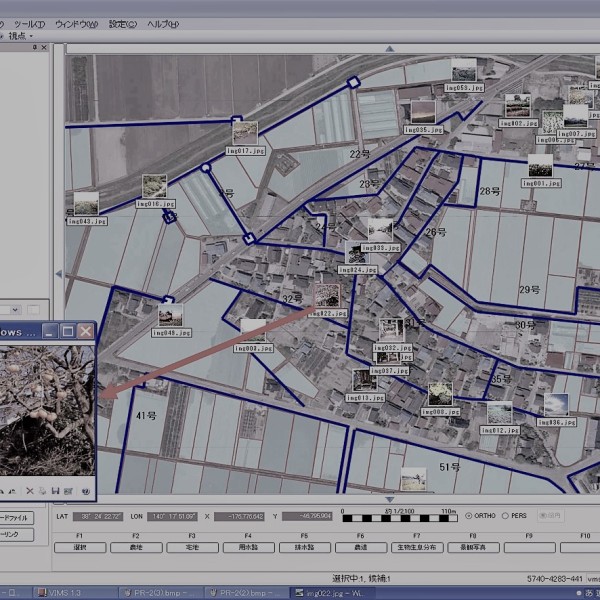
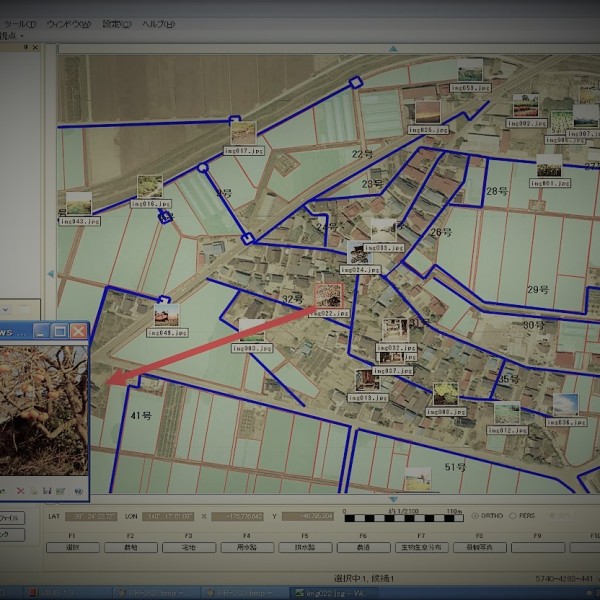
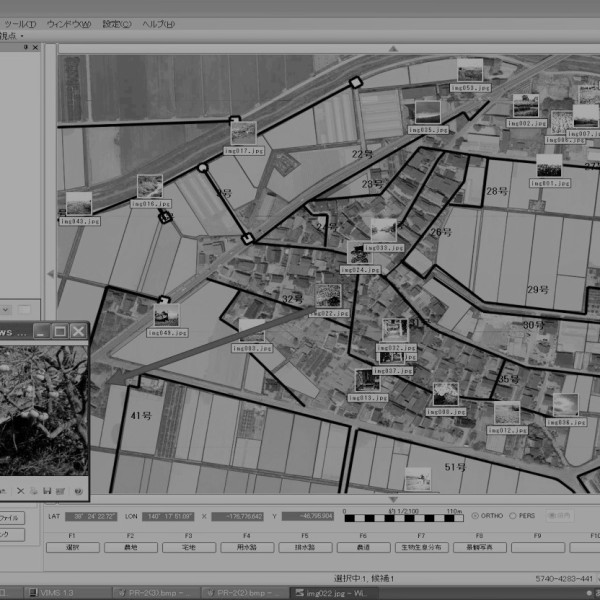








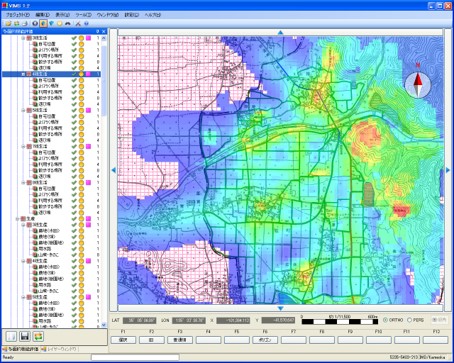
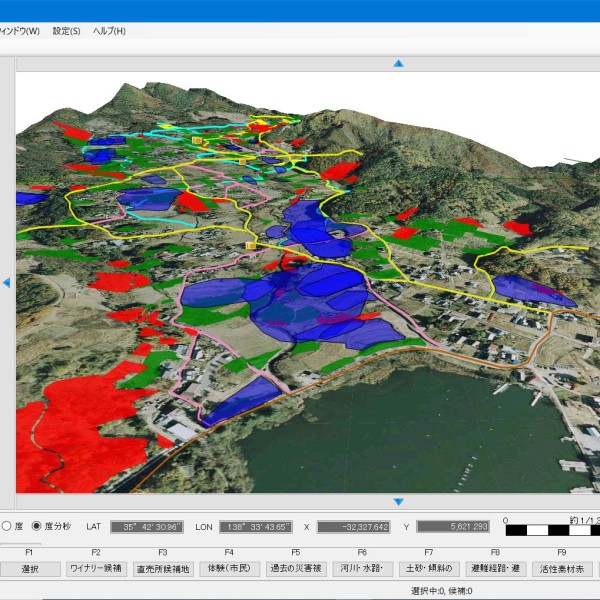
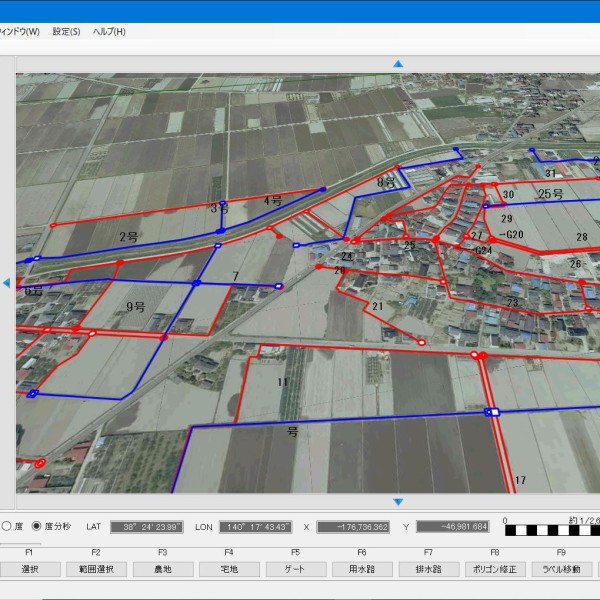


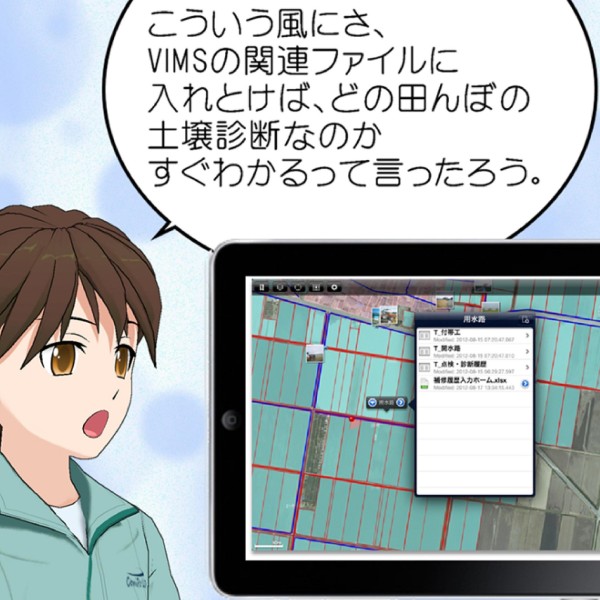

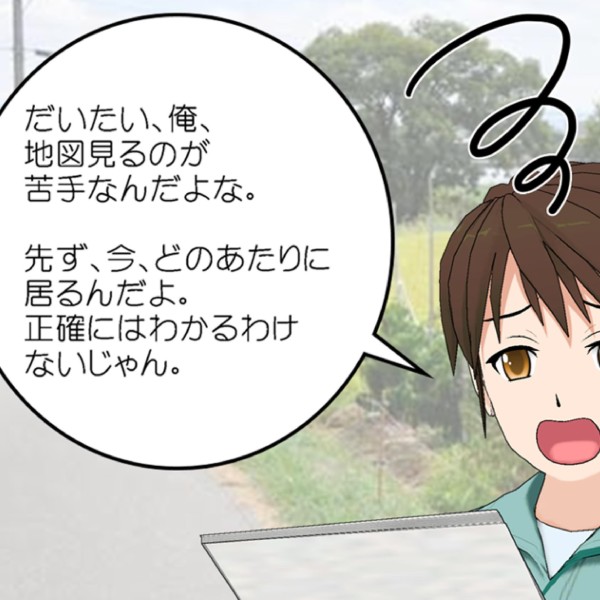





この記事へのコメントはありません。