
花見の精神
今年は、サクラの開花から満開までの期間が長かったようです。『花冷え』という言葉にもあるように、花が咲き始めてから満開までは寒い日が多く、花は長持ちするものの、花見をするにはちょっときつくて、おでんやけんちん汁だけでは堪え切れなくて、酒が入らないと、そして、夜ともなるとちょっと手拍子での踊りなどが入らないと、身体が保てない。
特に今年は、著しく寒い日が続いたということではないだろうか。私の住むつくば周辺は先週日曜日辺りがどこの公園も満開でしたが、9日になってもまだ葉ザクラとまでは行っておらず、散り始めのところがあり、小、中学校の入学式が終わったのでしょうか、新入生が両親や祖父母とともに校門前の桜で桜舞い散る中、写真を撮っている光景が見られました。ランドセルにサクラは何故かよく似合います。家族みんなで写っている写真も良いけれども、ランドセルが重いのか、緊張しているのか、ちょっと後ろに引っ張られそうになって、後ろに反っている小さな一年坊主の横向きの笑顔も絵になりますね。家に帰ってから、思わず、もう20年以上前の息子たちの入学式の時のアルバムを引っ張り出して見入って、なんだか泣けてきました。
それにしても、ニュースを見ていると、花見のマナーは最悪ですね。場所取りのいざこざはあるわ、宴会飲酒で暴れる奴はいるわ、それはまだ人間どうしのことなので良い方で、枝を折る奴、木に登る奴、木を揺すって無理やり花吹雪にする奴、とにかく、花に対しての感謝の心がまったく感じられない。一番ひどいのはゴミですな。そのまま、サクラの木の下に捨てて行く奴がいるって言うんだから情けないたらありゃしない。
かなり古い話ですが、M市のある集落で農村づくりのお手伝いをしている時に花見にまつわる美しいお話を聞かせてもらった。その集落には女性メンバーだけで結成した農村レストランがあり、美味い山菜の天ぷらなどが食べられるというので、M市内からはもとより、名古屋や大阪からも少しずつ客が集まってきていたらしい。ある春の日、M市内から食事に来ていたS氏が、レストランで食事をしていたところ、里山の中腹にたいへん綺麗で立派な山ザクラが咲き誇っているのを見つけました。「あのサクラは素晴らしいですね」とレストランの経営者に言ったところ、経営者であった地域リーダーのN氏が、「よろしいやろ。うちらの集落の誇りですわ。昔はあそこの下まで行って、花見してたんやけど、人おれへんし、今は山も荒れてしもうて、あそこまで行く道がもうのうなってるんですわ」と答えた。そして続けて、「あのサクラの下辺りに花見台でも作って、真下から鑑賞したいなぁと思うてんねん」と長年の夢を語ったんだそうです。
S氏は、その話を市内へ持って帰って、いろんな仕事仲間たちに話をして、山の管理を手伝って、最終的には花見台を作ってみませんかと呼びかけたのです。話はとんとん拍子に進み、どれくらい時間がかかったのかは忘れましたが、下草刈りを徹底し、道を整備し直し、展望台までとは行きませんでしたが、平らにした土地を作って、花見台にしたと言うのです。
花見をするために、山の管理を先ず徹底する。『花を愛でさせてもらうんだから、山を大事にするというところから始めよう』、この精神が素晴らしい。この花は、この山あってのものという考え方が心の中にまで染みわたっています。
木を傷つけて、ゴミまでおいて行く奴なんかに花見をする資格はない。金を払っているんだから良いだろうというのも違う。花見とは人と人のコミュニケーションの場ではなく、花、木と人のコミュニケーションの場であるのです。花と言う価値に金を払っていると考えるから、本来の花見の精神が有耶無耶になり、花と木が大切にされない。そして、マナーなんてもので行動を規制しなければならなくなる。人の木に対する感謝の心を再認識させてくれたこと自体に代価を払うべきであって、それは自然と溢れて来るべきものなんだとこの話を聞いた時に感じました。
コメント ( 0 )
トラックバックは利用できません。
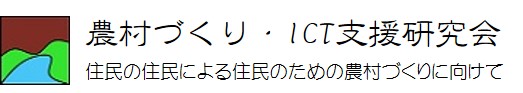









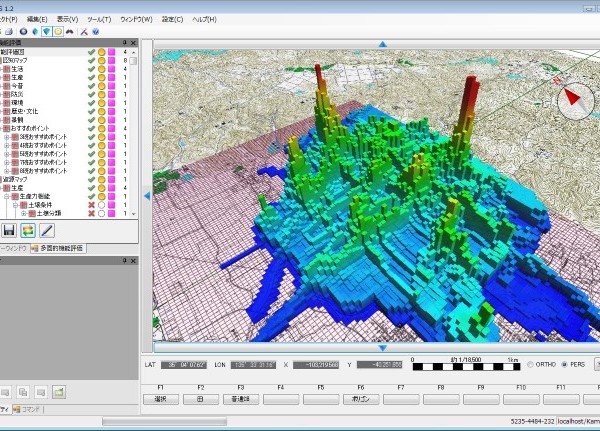










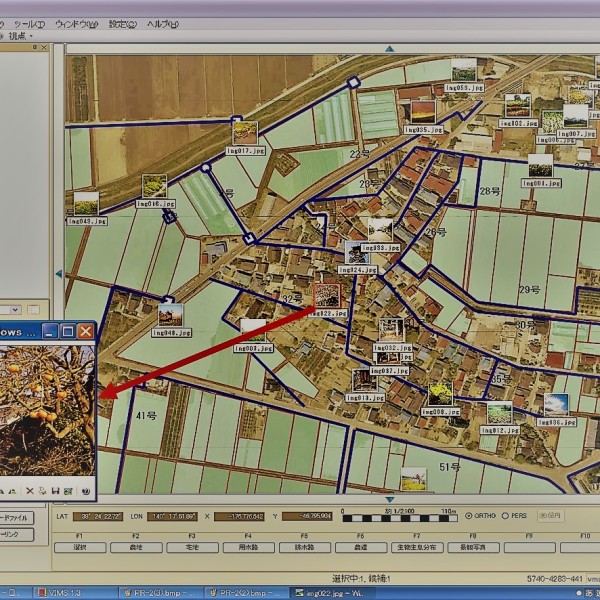
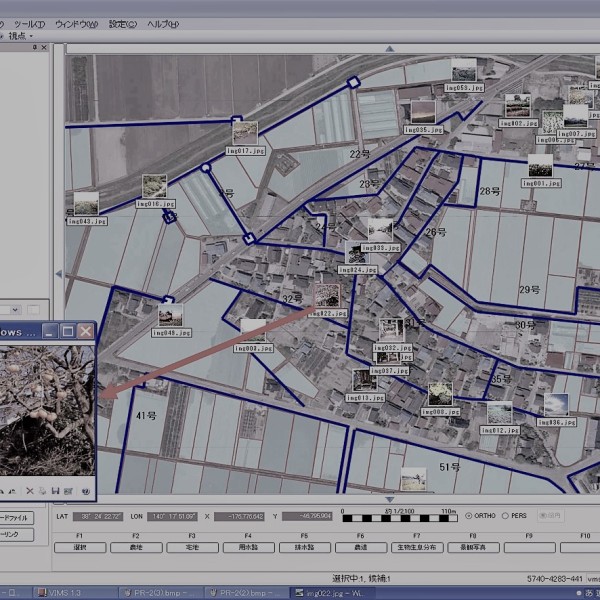
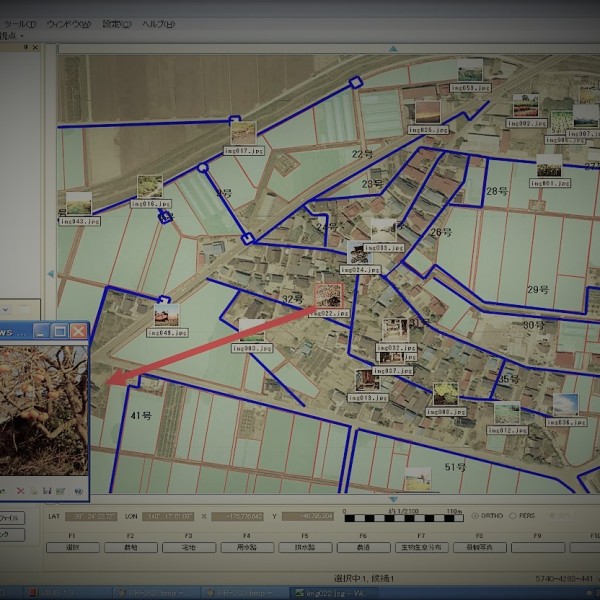
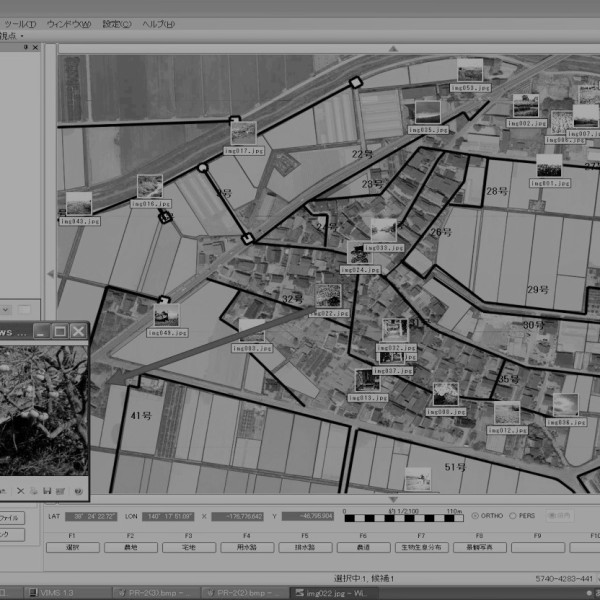








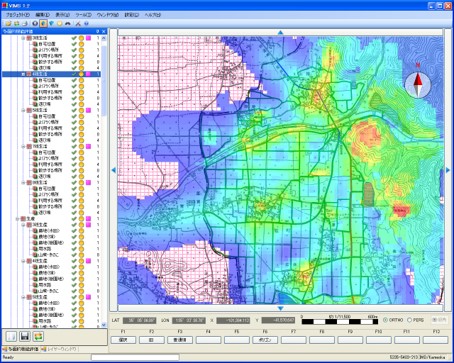
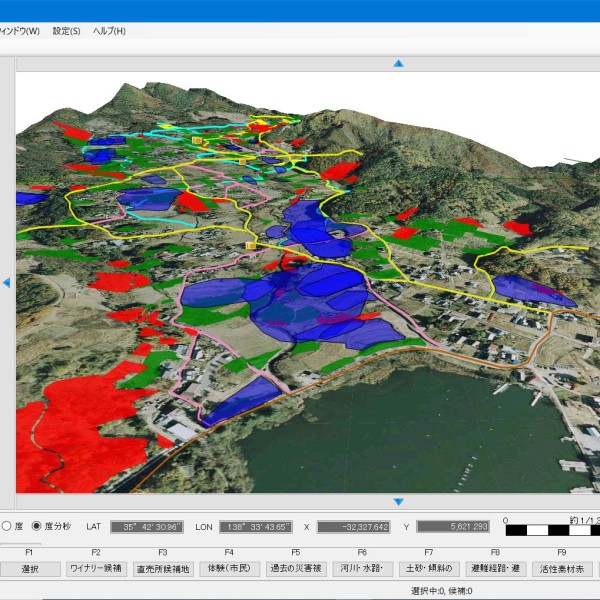
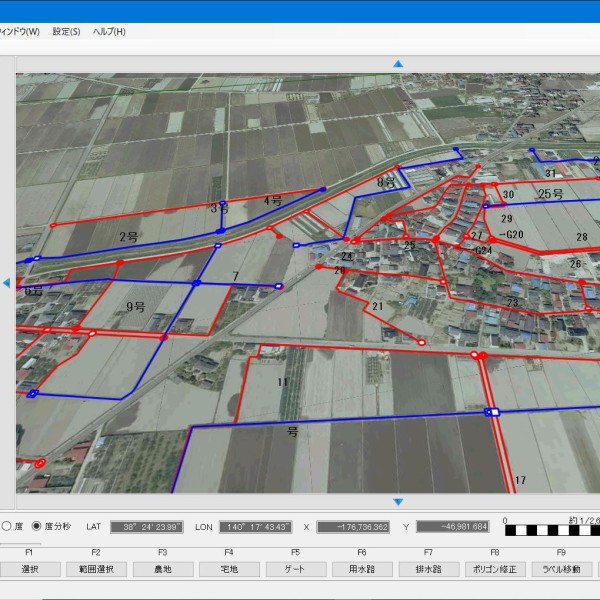


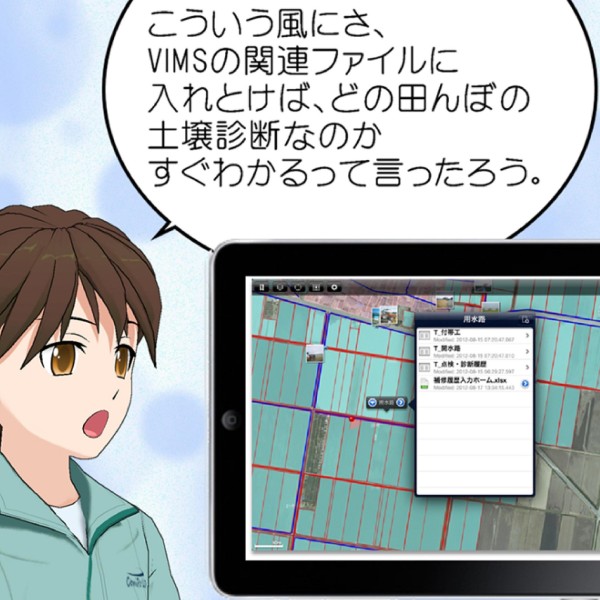

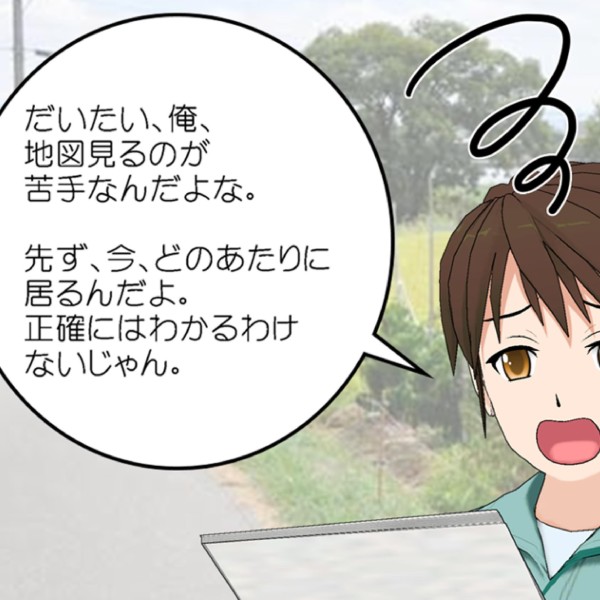





この記事へのコメントはありません。