
農業の国民理解
NHKのネタドリという番組で米の増産問題が取り上げられていました。増産のためには、担い手への土地の集約化、農地整備などの土地改良事業による大規模化が必要であるが、所有者不明地がネックとなって、事業が思うように進まないことや担い手・人手不足に対応し、先端技術を活用したスマート農業の導入支援などが挙げられていました。
内容を聞いていて、ちょっと呆れたというか。20年前となんら変わっていないことに驚いてしまいました。問題自体が変わっていないというか、以前よりもシンプルに表現されていると思いました。これは長い年月をかけて、農業にそういう問題があるんだと言うことが、徐々に浸透してきたと言うよりは、今回の米の価格高騰に伴って国民が一気にその問題を認識しはじめたということみたいです。
兎に角、問題は20年前と何も変わっていないのです。私の農業土木技術研究者の現役時代も入っているので、国民への問題意識の共有化の努力が足りなかったという事ならば、私にも責任の一端があったと思わざるを得ません。専門家はみんな分かっていると思い、問題を解決しようとしますが、国民からしたら、何か専門家がよく分からんことをしているとしか見えていないと言うことのようです。『技術というのは、国民の理解を得て初めて前に進むものである』そんなことは分かっていたはずなのに、私たちはそのことを十分理解していなかったということです。技術開発の専門家としての立場から一国民となった今、ようやく本当のことが分かってきたということです。国民の理解というのは、我事感としての浸透度が大切なのだと。
米の価格の高騰という我事感があって、はじめて、その問題を解決するための問題の重要性が実体化し、技術や制度の意味が真に理解され、ようやくそれを解決するための対策がなされる。これまでも対策は成されて来たし、多くの事業へ金がつぎ込まれ、制度改革があった訳ですが、これらは専門家レベルの施策ということになります。国民によって噛み砕かれた施策ではないのです。重要なのは、国民レベルで施策の意味が伝わることなんだと思います。
ニュースの中では、最後の方で、規模拡大が不可能な中山間地域での生産性向上と空間の持続性の課題として農業・農村が持つ多面的機能への理解についても触れられていましたが、こんなことも、平成11年の食料・農業・農村基本法の改定時にすでに言われてきたことで、「今更、またそれかい。なんも進んでいないなぁ」と悲しくなってくるのですが、違うのです。十分進んでいるのです。農業というサイドから国民というサイドに問題がようやく降りてきたと言う事で進んでいると考えるべきです。
昔、農家の方と多面的機能についてのお話をしている時に、よく彼らから、「都会の人どころか、農村部でも農業者ではない人に対しては多面的機能の意義が伝わらない」と聞いたことがあります。私も講演会などで多面的機能の重要性についてお話などさせていただきましたが、それは単なるお話である。水田の持つ洪水調整機能としての田んぼダムの取り組みなどは、被害が我が身に降りかかってようやく、田んぼの機能は大事だなぁと思う訳で、なんにも利を受けていない多くの国民からしたら、「田んぼダム、なんぼのもんじゃい」ってことになるのです。
昔の友人で、都市部で中学校の教師をやっている人に「農業の多面的機能について子供たちと話し合うことがあるか」と聞いたことがありますが、この時も、「農業そのものを知っている訳では無いので、子供たちはみんなきょとんとしているよ」と言っていました。「それこそ、大好きなお米が高くなって食べられなくなって初めて、農業どうなっているのだろうって考えるのであって、そこそこ問題なければ、問題意識は持たないだろう」と言っていましたが、その通りである。
かといって、国民みんなに米も買えなくなって、毎年洪水で苦労してと、困難が降りかかるべきだとは言いにくいので、他人事感を我事感にする訓練をして、『暮らしの知』の共有を図りましょうと、私なんかは言うしかないのですが、今回、米の価格高騰と増産問題は誰もが我事感にし易い例となった訳ですね。徴農制となると過激すぎますが、こういう風にして、国民総農業者意識が進むことは望ましいことなんでしょう。技術だ、施策だと言わずに、先ずは農業の国民理解をそこに持って来るという側面を作るだけでも農業構造はだいぶ変わるということかも知れません。
コメント ( 0 )
トラックバックは利用できません。
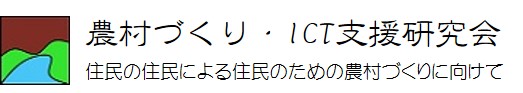









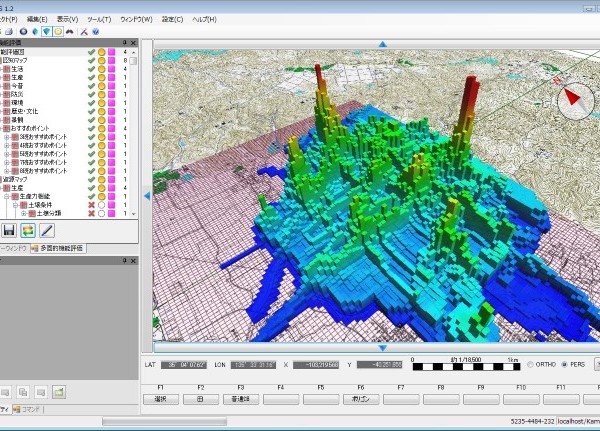










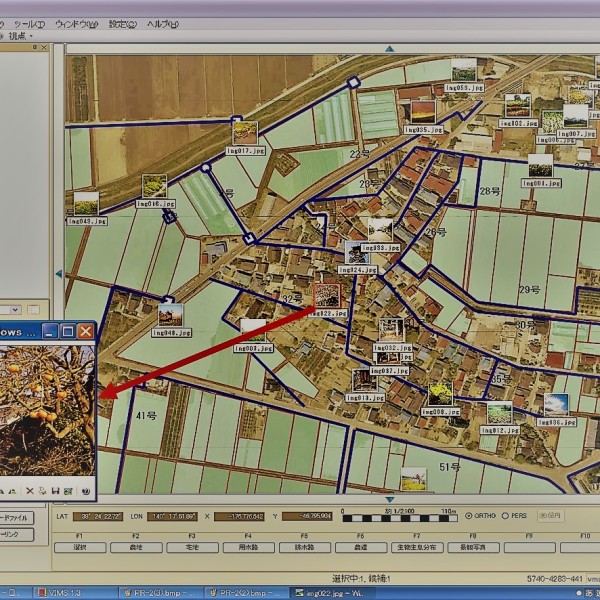
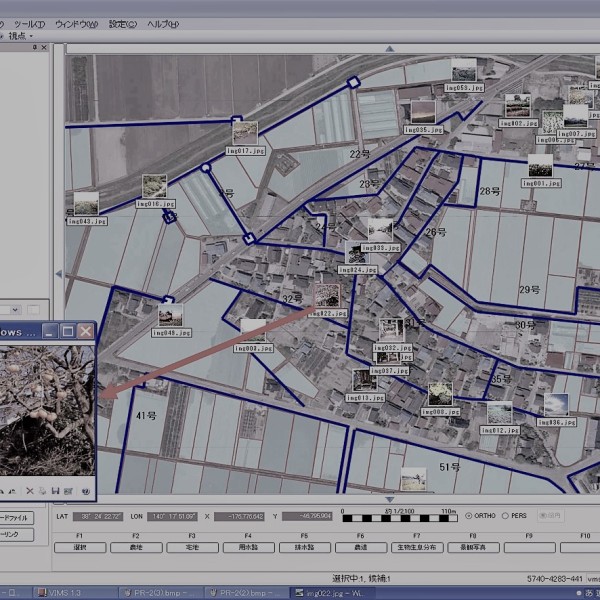
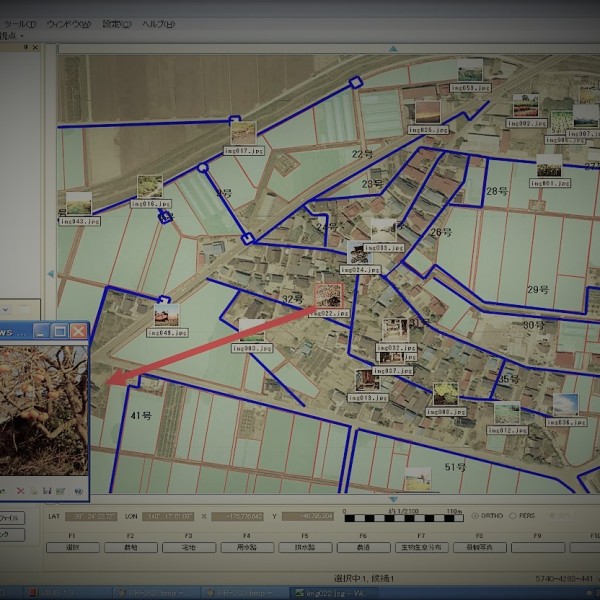
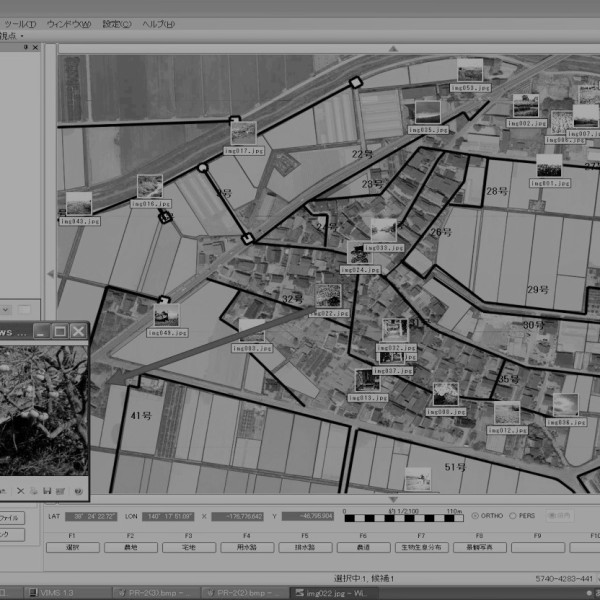








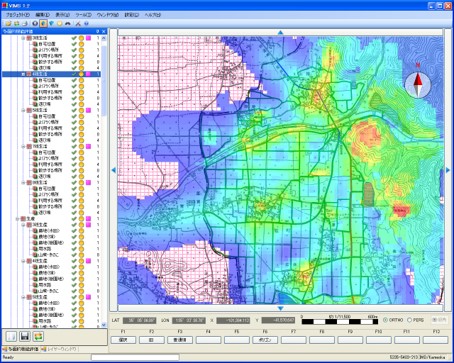
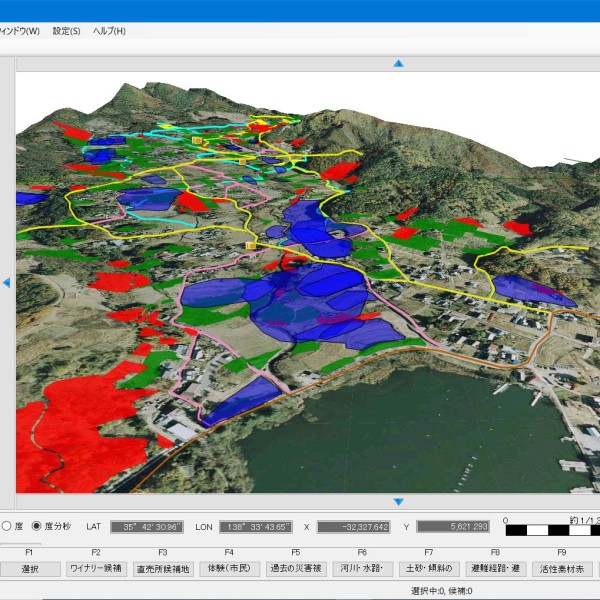
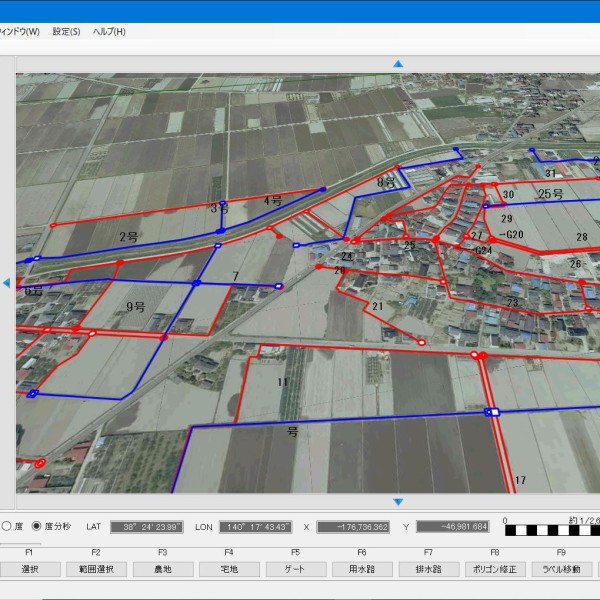


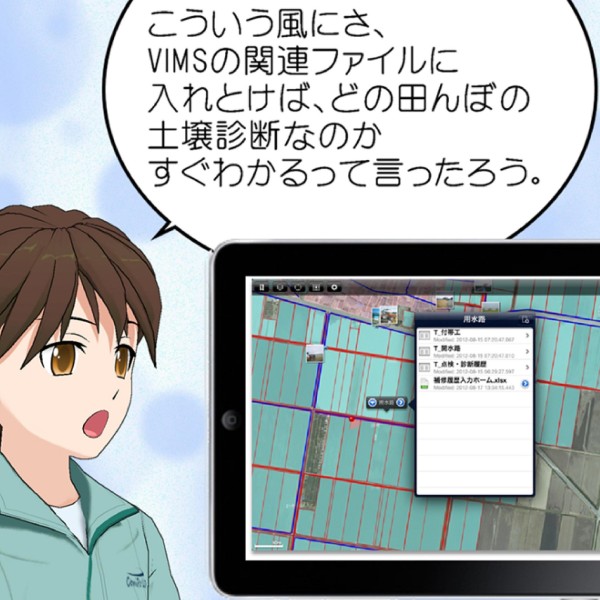

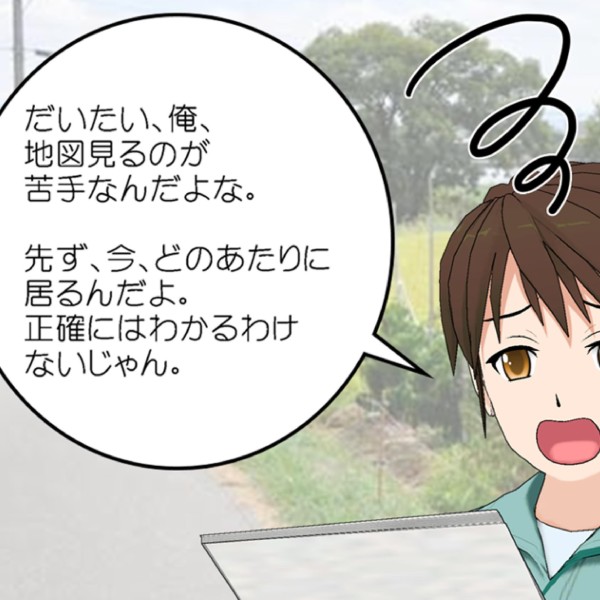





この記事へのコメントはありません。