
集落環境整備について考える視点(7)
7.長期ビジョンの樹立を
それぞれの市町村では、市町村全域を対象とする長期の総合計画としての市町村計画や農村総合計画を策定しています。しかし、市町村内の農村地域の地区計画や集落計画といった狭域の地域計画を総合的な視点で策定している市町村はまだ少ないと言えます。農村環境整備を地域の将来的展望に立った活性化に位置づけていくためには、これら地区計画や集落計画、さらには特定の空間の場の計画が、前もって具体的に、かつ環境のイメージを含めて計画的内容で策定してあれば、極めてスムーズにそれを進めて行くことができます。つまり個々の事業の計画を開始する前に、市町村レべルから狭域レべルの環境単位まで含めた長期計画を各々の視点からも計画しておくということです。確かに、社会状況は変化し、それに伴って計画も変更を余儀なくされる場合もあるでしょう。しかし、事前のビジョンの樹立とそれに伴う計画の立案は、その後の修正のためには極めて大きなかつ重要な情報のストックであり、その後の展開に大きな役割を果たします。
一般に自治体が係わる環境整備の事業の計画期間は行政の事業執行のシステムのもとで一般的に短い。一方では整備を進めるにあたっては、様々なことを検討しなければならないとともに、そのための調査や創造的なエ夫が必要となってきます。農村環境整備を農村の特質をいかし、地域の特性を生かし、量から質への転換する整備には、十分な調査と計画の時間が必要となってくるのです。又、いくつかの空間要素や事業の組み合せを行い、かつ関係機関や住民の整備に対する理解を得るためには、より一層の十分な計画が必要となります。
整備は一度行ってしまうと、良きにつけ悪きにつけ壊すことはもったいないし、又、さらに金もかかる。つくる前に、整備する前に十分時間を費やすことである。それが10年後、20年後に生きてくるのである。
早急には困難であるとしても、時間をかけてそれぞれの地域で独自の長期整備計画を樹立していくことが必要である。さらにそのことは、それぞれの地域の子どもたちをも含めた住民の環境教育としても機能することとなります。
完
コメント ( 0 )
トラックバックは利用できません。
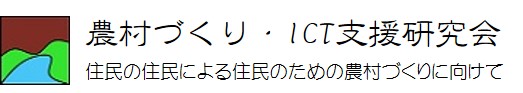









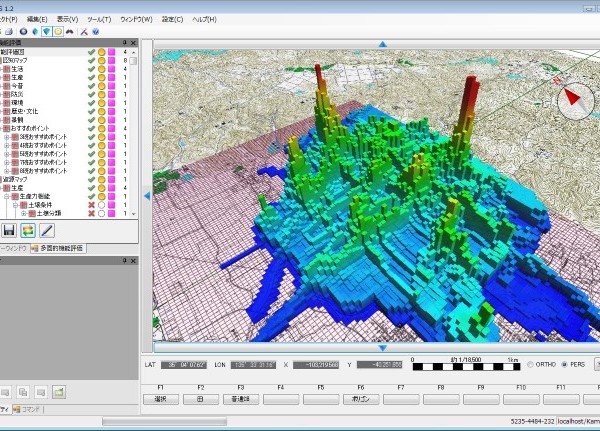










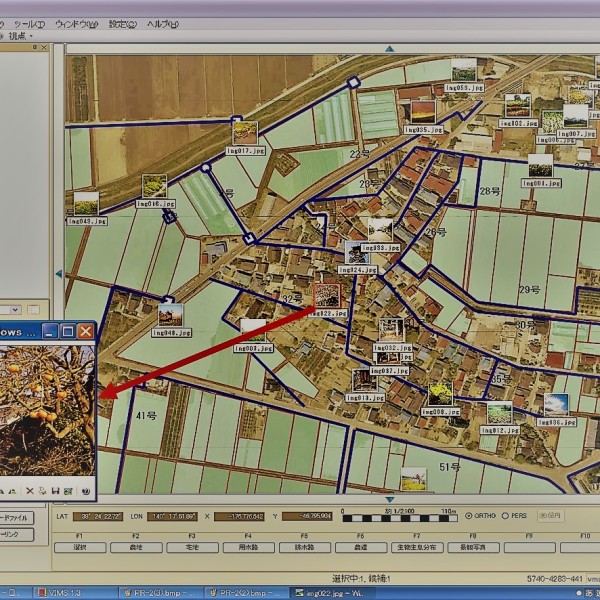
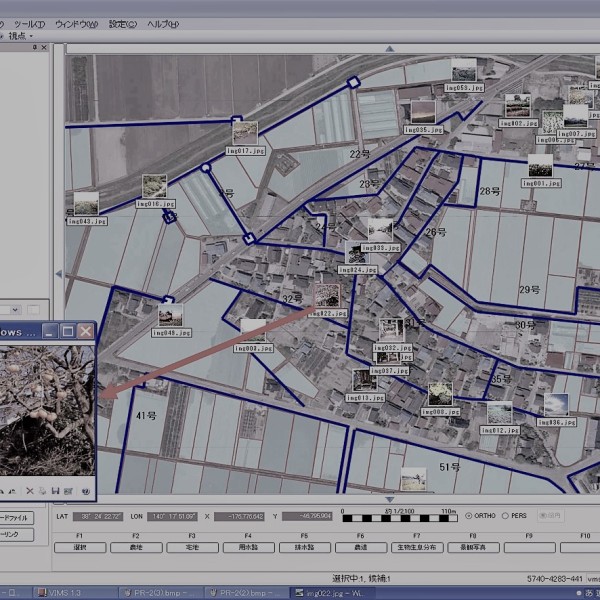
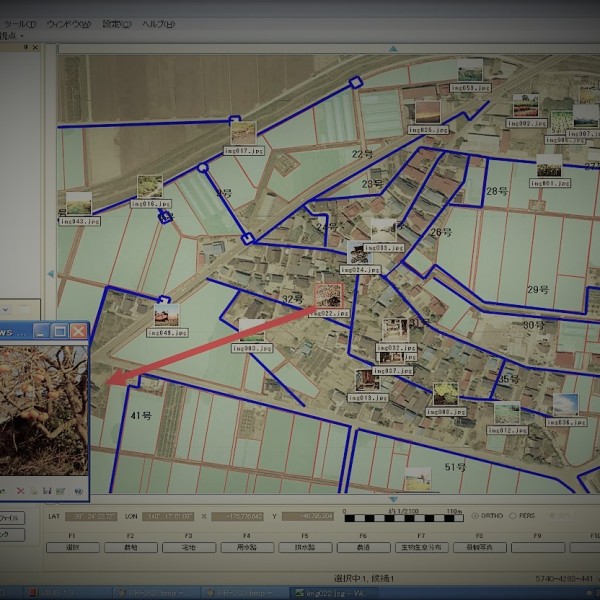
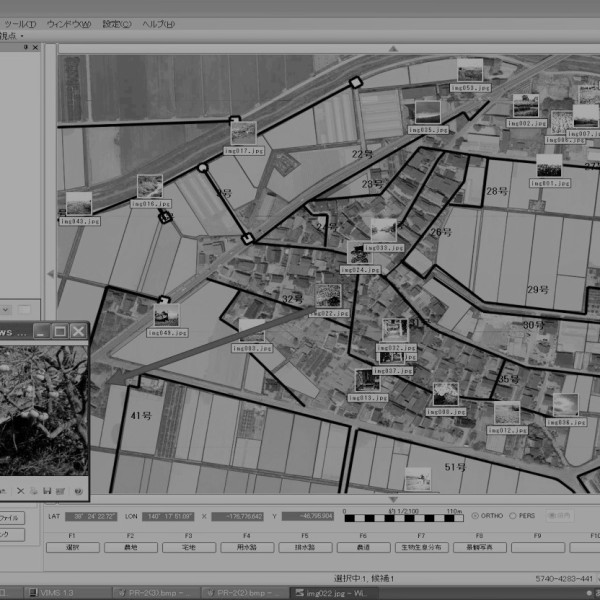








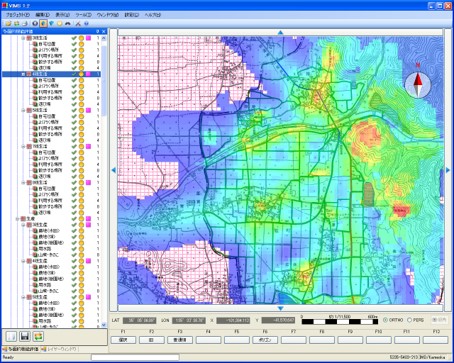
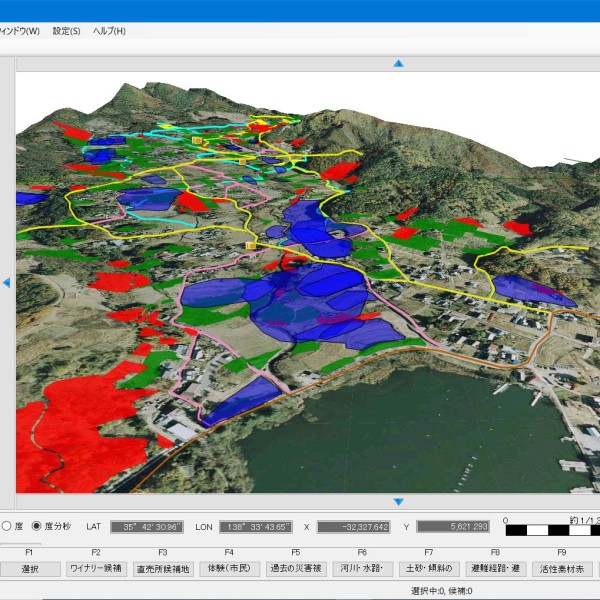
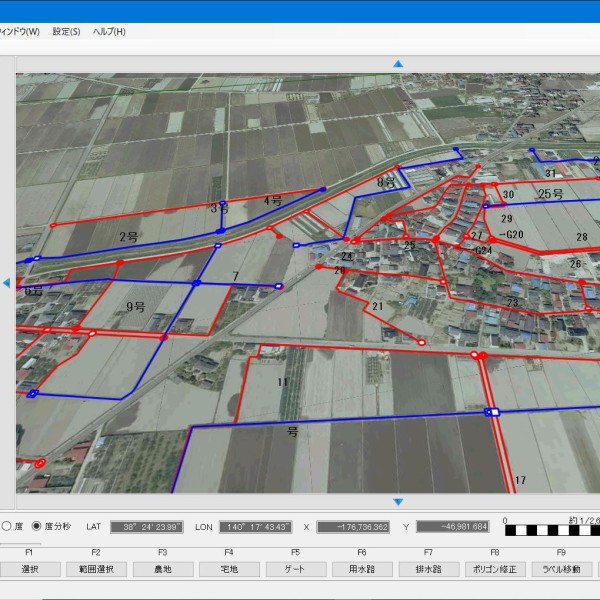


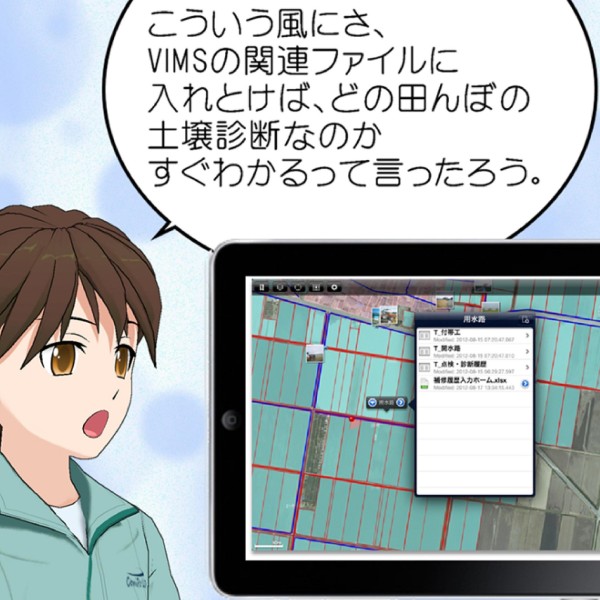

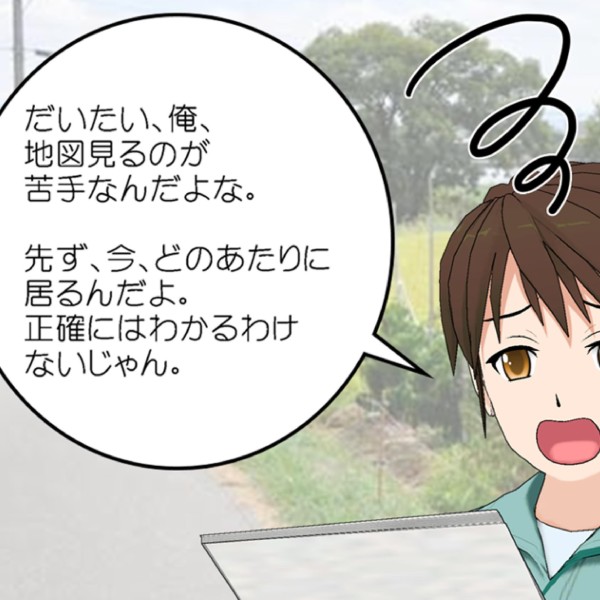





この記事へのコメントはありません。