
集落の環境整備について考える視点(4)
4.部分的整備を全体的整備の中に位置づける
これまでの農村地域における整備は、農業の生産性の向上という命題の下に行なわれ、当然ながら、生産基盤整備が優先的に行なわれてきました。それゆえに、生活及び生産の両面を視野に据えた、総合的な整備とまでは言いがたかった。総合整備事業以降の事業においては、生活環境整備の対象資源は、生活全般を対象とするために生産基盤整備に比較すると種類が多い。多くの種類の中から、ある整備対象資源だけを部分的に取り上げて行う整備事業が、しかも他の事業と全く関連性もなく行われることが、現在までにも多くみられます。その一つの例としては、公園、集会所・センター等の整備計画における用地の捻出方法があげられます。このような施設の計画において、計画上望ましいと考えられる位置があったとしても、すでに圃場整備事業が完了したために、用地はおろか、位置についても、計画的に入手することができないという例です。結果的には、整備の対象となった資源の整備・活用のされ方はともかく、他の資源との望ましいと考えられた関連性を失うことになります。例えば、公園や集会所等と景観的価値のある位置や、利便性からみた位置や道路等の関連性などです。 今日までにみる整備結果は、決して資源の機能が単一利用になっただけでは止まりません。資源間の関連性も分断されることになったのであり、そのような結果を招いた一つの原因は、各整備事業の関連性や、各事業との全体計画との関連性の無さにあり、その結果きわめて個別的な整備事業となってきたからです。 地域の環境を構成する各資源は、それぞれがきわめて性格の異なるものである。その上、資源を個別にとり上げて、個別の課題解決へ向けて整備事業が行われると、全体としては何の脈絡のない異質性だけが露呈した整備になるのは当然です。昔と比べるとよく考えられるようには成ってきているが、再度、整備結果の集積としての環境体のあり方を考えておく必要があります。 今日望まれる農村地域の整備課題は、各整備対象資源の集合に何らかの共通した性格をもたせて、全体としてある特徴を生み出そうとするもの、又農村地域のおかれている地域性をも表現するための整備のあり方を整備技法に反映していくことそのものと言えよう。 しかし、全体の計画で、部門計画をあまりにも細分化すると地域性や整備技法が均質なものとなることに留意する必要があろう。部分を通して全体を組み立てる視点も必要であろう。
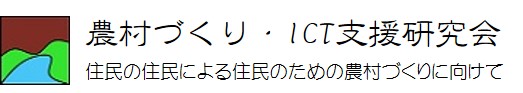








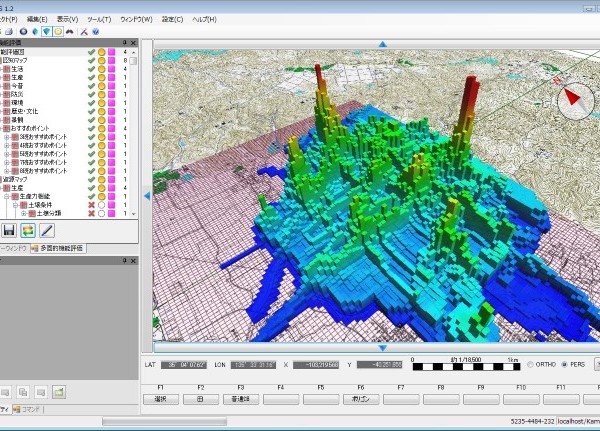










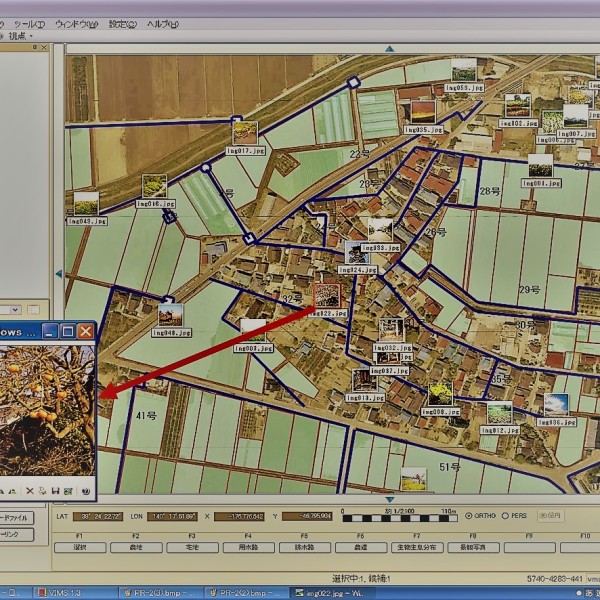
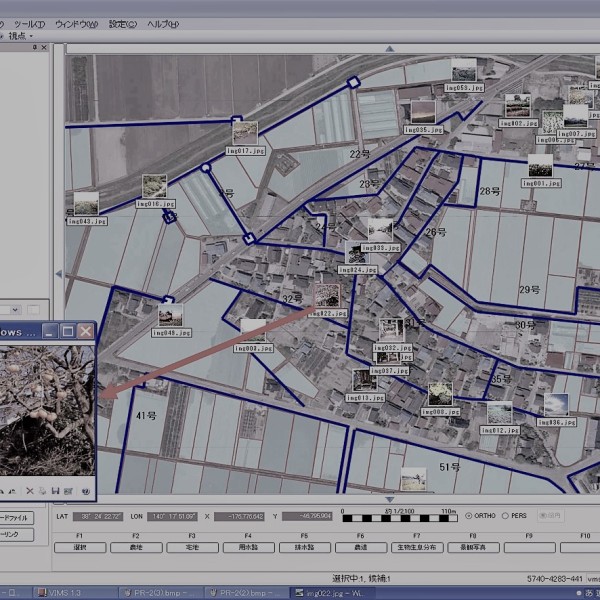
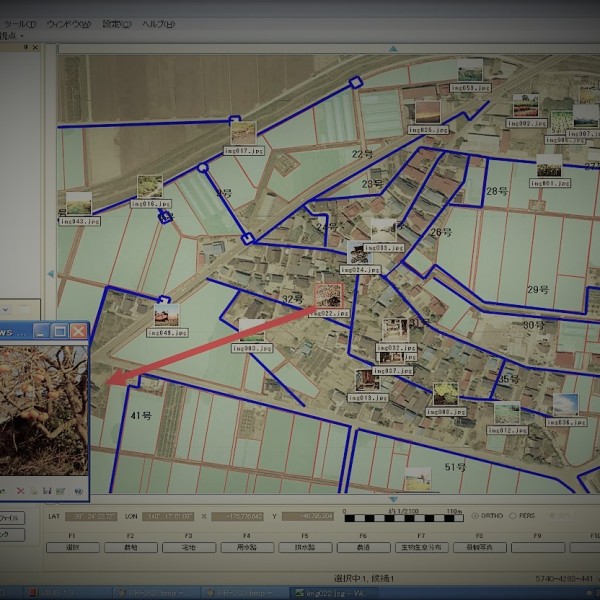
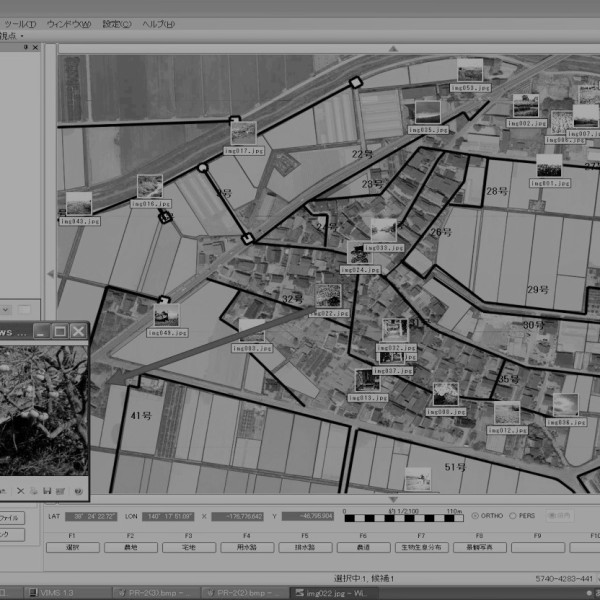








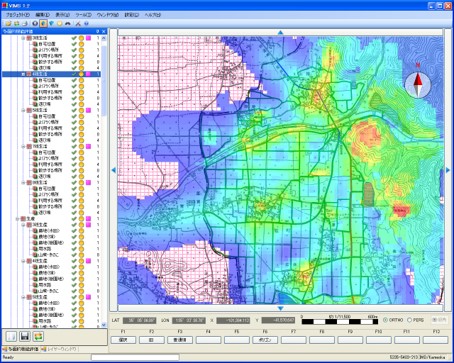
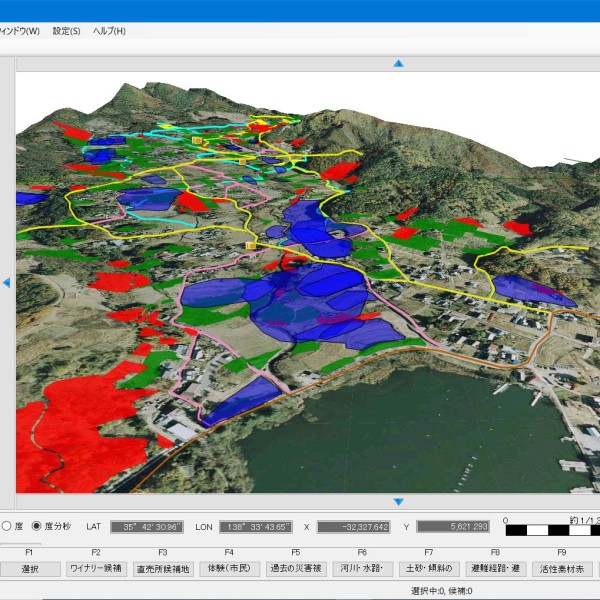
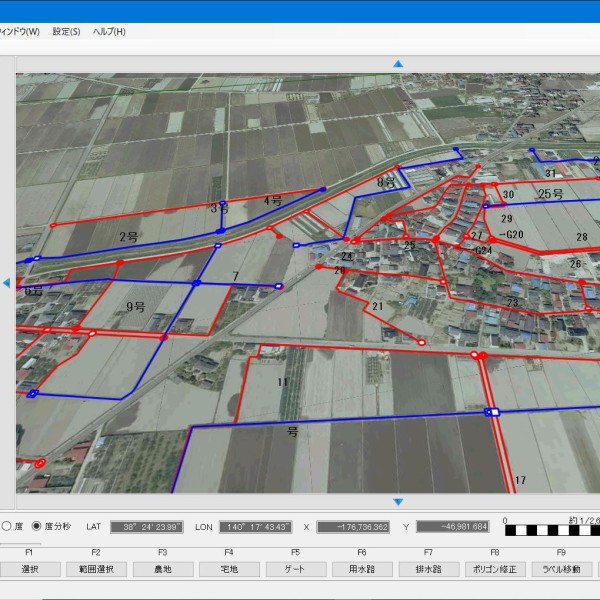


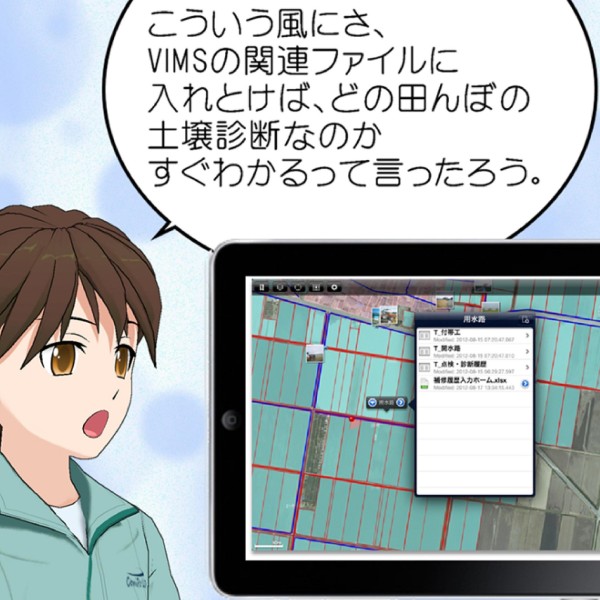

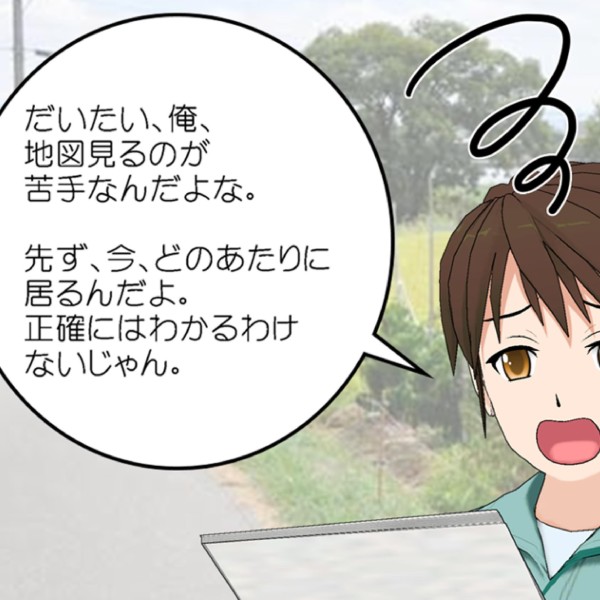





この記事へのコメントはありません。