
集落の環境整備について考える視点(3)
3.地域特性を生かし多様な整備へ
環境整備においては、まず初めは、環境の水準が著しく遅れている整備が優先されます。農村にあっては、曲がっていて小さな田んぼの整地と規模拡大や集落道路の拡張工事等にみられるように、先ずは機械化に対応できる圃場の整備や最低限の道路の通行機能の確保等、「低水準にある施設・設備の水準をポトムアップ」することに重点がおかれ、効率的整備が要求されます。 しかし、それらの整備には、地域が有している社会的または空間的な特徴を配慮した「快適な環境」を形成する計画理念は希薄です。
つまり、地域特性を考慮した質的整備に関しては、大きく立ち遅れているばかりでなく、極端に言えば、量的整備によって、これまで地域が培ってきた文化・歴史性などを破壊してきたとも言えます。また、農林水産省に限らず各省間の縦割り事業のもつ欠点もあり、いずれもが単独事業となり、何ら相互関係をもちえない、ただ単につくることが目的化された事業が多いと言えます。 作ることは目的ではなく、あくまで手段であるということを忘れてはいけません。目的はあくまで地域住民のアメニティであり、地域の活性化なのです。その目的を達成するために整備が行われるのであるということを認識しなければなりません。 農業の生産を発展させながら、混住化が進行する農村社会、高齢化が進行する農村社会、若年層を迎えていく農村社会に応えていくために、農村や地域文化の特質をいかした農村環境整備を進めて行かなければなりません。だから多様な農村環境整備が必要なのです。それは、地域の空間機能の複合性の追求、地域の景観形成の追求、地域の自然との係わりの追求、地域の歴史・文化との係わりの追求、地域の主体との係わりの追求です。 農林水産省の事業は農業とそれを担う農業者への対応ということではありますが、今や農村と言っても混住化の進展により農家は少なく、逆に非農家が圧倒的に多い地域すらあります。農村全域を考えた上で、単に農業だけでなく地域社会つまり・・・農村全体を考えて多様に対応する必要があるでしょう。
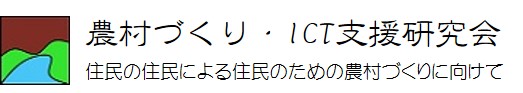









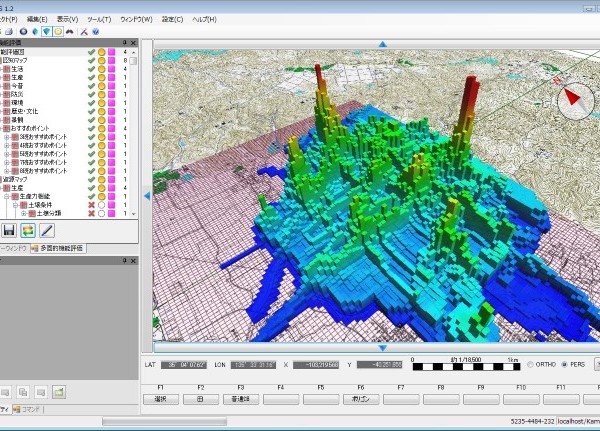










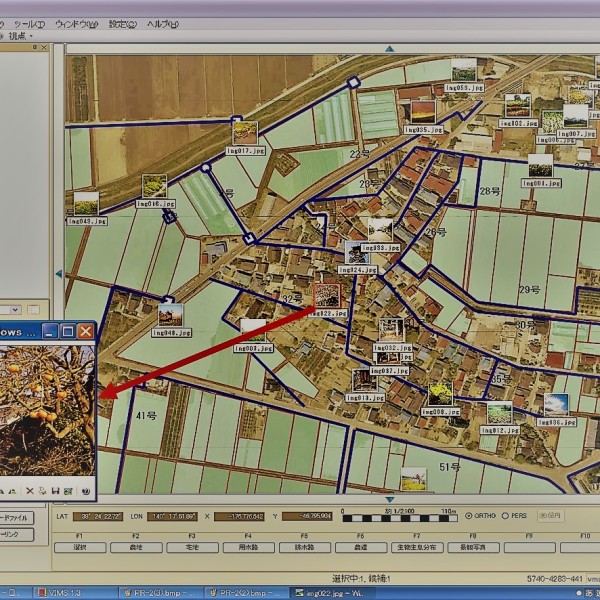
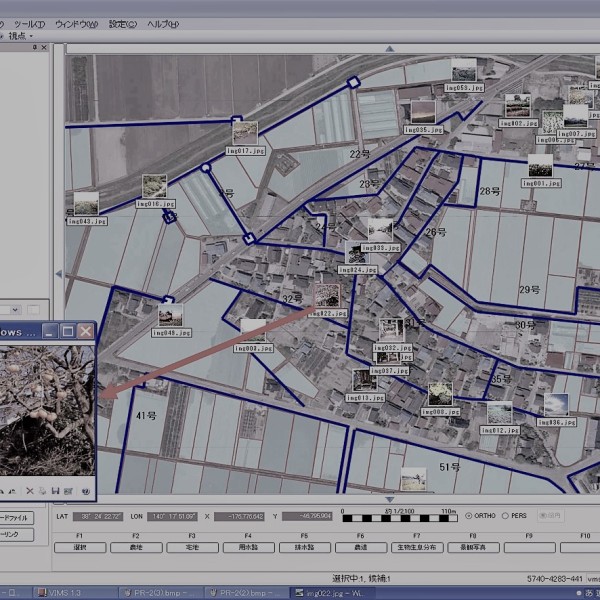
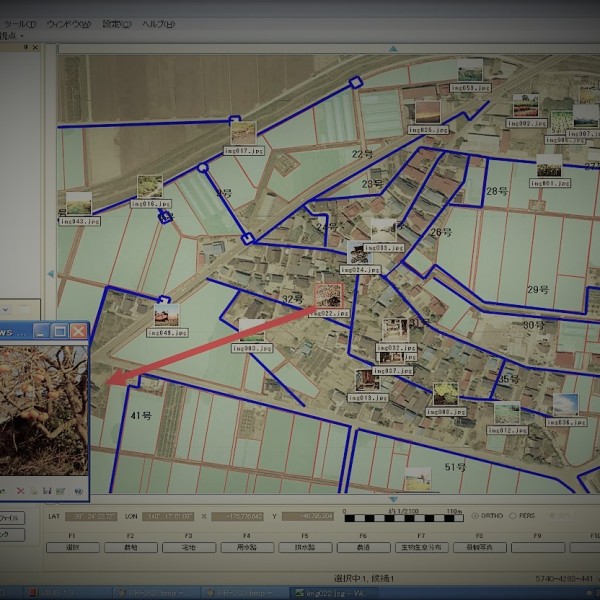
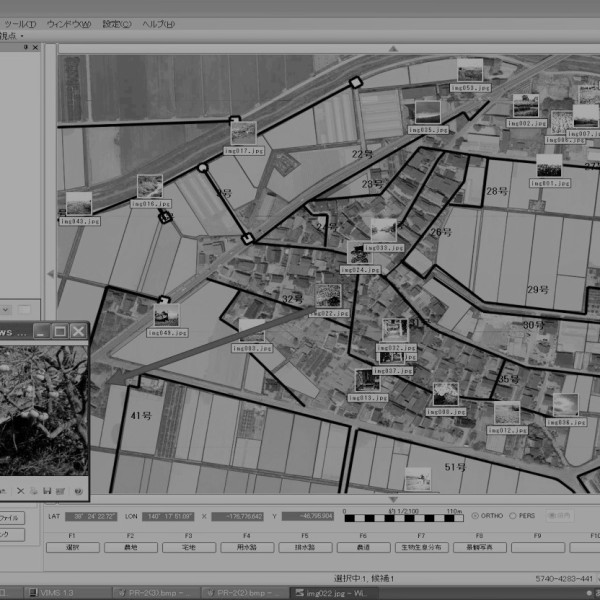








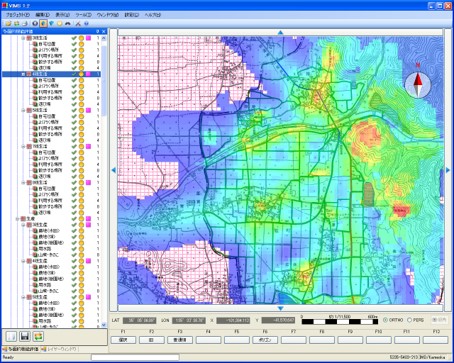
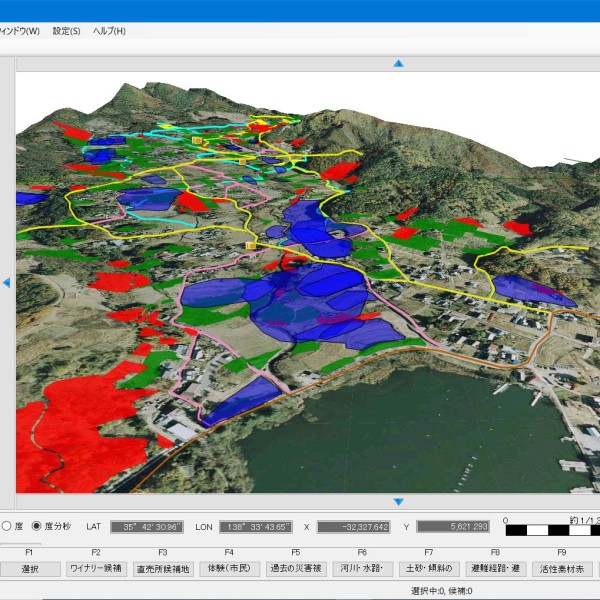
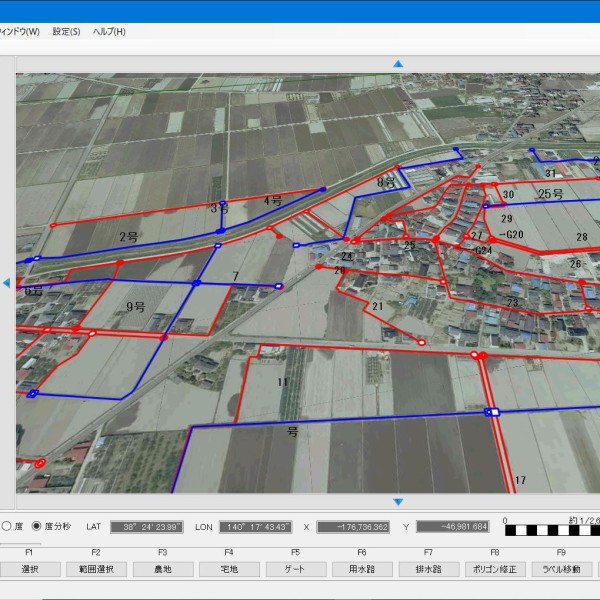


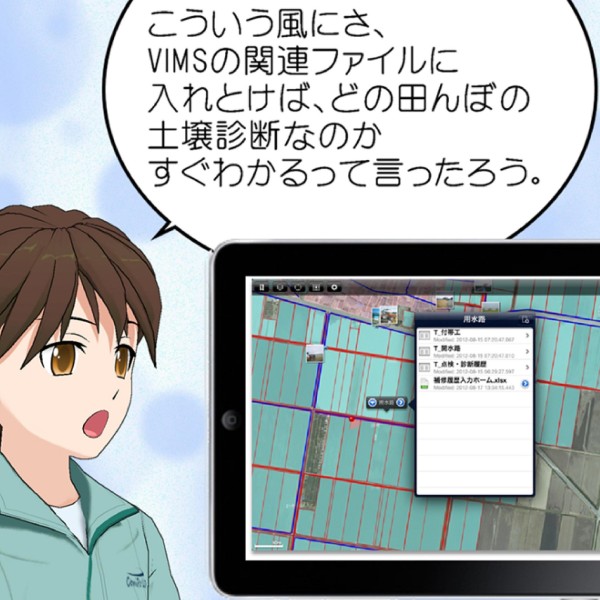

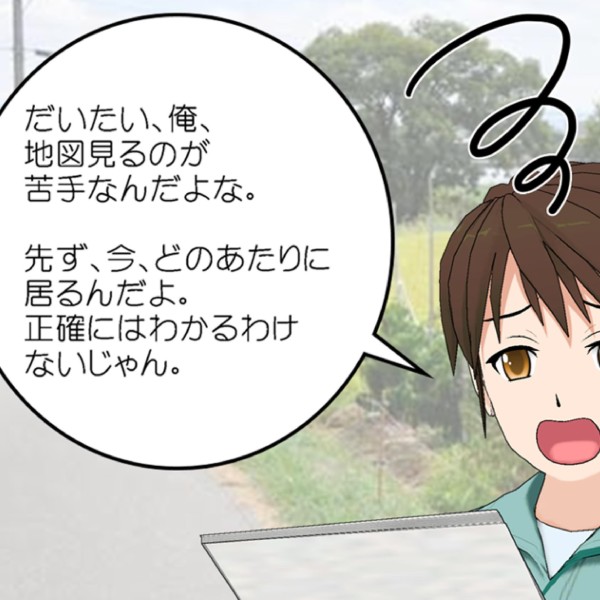





この記事へのコメントはありません。