
戦争体験
戦後80年を迎え、戦争の記憶の継承についての課題が浮上しています。これまでも、メディアは戦争の記憶を忘却することなく、継承し続けることの重要性に注意を喚起してきました。しかし、戦後80年ともなると、戦争の直接的な体験を語る人はかなり少なくなってきていて、今や、戦争体験者は9%程度になってしまい、継承そのものが困難となっています。また、厚生労働省によると、被爆者健康手帳を持つ被爆者が3月末時点で99,130人となり、最多であった1981年の4分の1になり、初めて10万人を下回り、平均年齢は昨年より0.55歳上がり、過去最高の86.13歳となりました。広島、長崎の原爆のあの悲惨な記憶においても、語り部による生の声は小さくなって、だんだんと風化せざるを得ない状況に陥ってきていると言わざるを得ないのです。
こうなると、もう先の戦争は歴史の一幕であって、ちょっと前までは現代史として少し別扱いされていたようにも思うが、いよいよ、源頼朝が鎌倉幕府を開くって言うのとたいして変わらない次元に追いやられているのかと思うと、悲しくなってしまう。いや、腹立たしくなってしまう。妻が塾で小学生を教えているので、この時期になると毎年、「みんな日本が戦争したことを、家で話したりする」って聞くらしいが、「話したことない」ならまだ良い方で、「ウクライナのこと?」とか、「北朝鮮が攻めて来るってパパが言ってた」なんて、とんでもない答えが帰って来て、日本が戦争をしたことを知らない子供もいるそうです。♪戦争を知らない子供たちさ~♪と歌うなら、戦争を体験していないだけで、戦争を意識していない訳では無いが、これは『本当に戦争を知らない子供たち』ということになってしまう。
なんて平和ボケした能天気な奴らだなんて今の子供たちを責めるのはいかがなものか。考えてみれば、私も小中学校の頃、両親や祖父母から戦争について話をしてもらったことがほとんどない。特に戦争を小中高の時に経験した高度経済成長期の親世代は「戦争のことを教えて」って聞くと、割と嫌がっていたように思います。だから、学校でもあまり話題にならなかったように思います。「日本が悪かった」とも明確に言えず、かと言って、「日本はがんばった」とも言えず、なかなか難しいところに置かれていたのだろう。もう亡くなってしまったが、母から聞いた話と言えば、「終戦の玉音放送で、親や近所のおじさんたちが突っ伏して泣いてたけど、私らようわからんかったわ」と言うだけだった。「『堪え難きを堪え 忍び難きを忍び』と宣われたのを聞いて、どうして堪え忍ばないといけないのか不思議だなぁと思った」と聞いたこともある。また、直接的な体験としては、九州の八幡に住んでいた親戚の家に遊びに行っていた時に、八幡空襲に巻き込まれ、焼夷弾の降り注ぐ中を走り回って逃げたとも聞いたが、私も平和ボケの子供だったし、大阪万博の好景気の波に大人たちと一緒に浮かれて、戦争を実感できないまま、「どうして」、「何故」、「どうして助かった」のと深堀りして聞き直すことが出来なくて、話はそれで途切れてしまっていた。大切なのは、事実を聞くことではなく、話した人の心の中に入っていけるかどうかということになる。
先日、テレビを見ていると、狩俣日姫さんという方が体験者と若い世代を繋ぐ取り組みが困難になる中、ロールプレイなどを活かして、新しい形の記憶の継承に挑んでいる姿が取材されていました。すばらしい活動だと思います。戦争体験の継承が戦争を知らない世代になされることは、永続的な平和社会の形成においてたいへん重要なことだろうことはよく分かる。そしておそらくは、第一は体験者から戦争体験を聞くこと、そして第二は様々なアーカイブやコンテンツに触れることが重要なのだろうが、基本的な問題は、如何に戦争体験を『我事感』にできて、単に「戦争は怖い、嫌だ」ということではなく、戦争を失くすめたには一人一人が何をすれば良いのか、平和を築くための思考はどうあれば良いのかに到達することになる。平和教育は体験者がいなくなればできなくなってしまうと言うことではなく、何を見て、何を聞いて、何を話し合って、自分の心の中に問いかける自分を作ることだろうと思うのです。
コメント ( 0 )
トラックバックは利用できません。
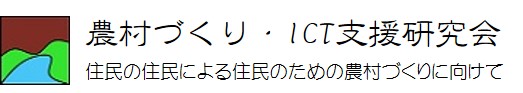









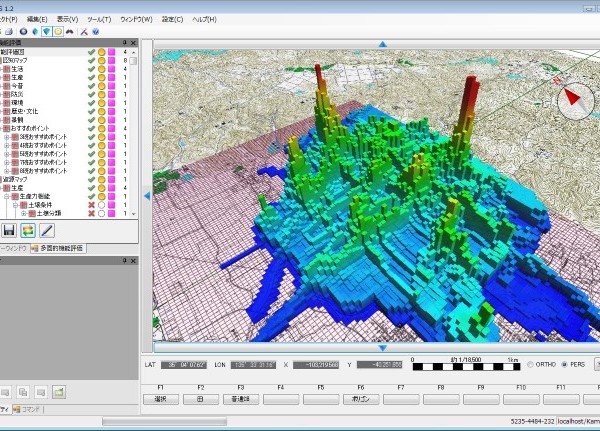










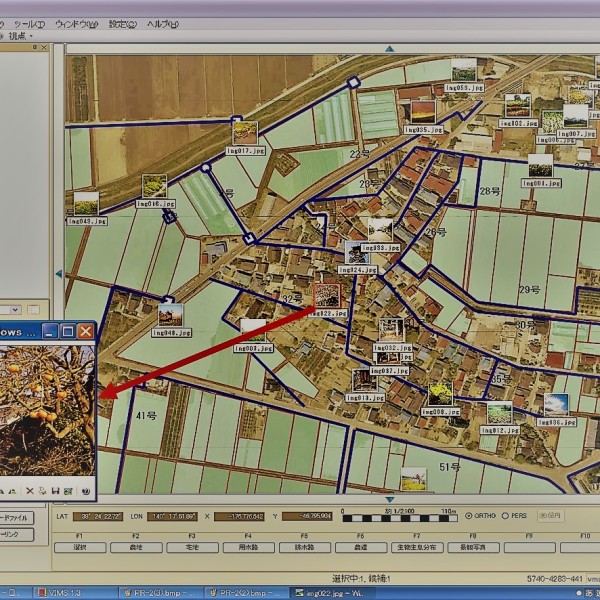
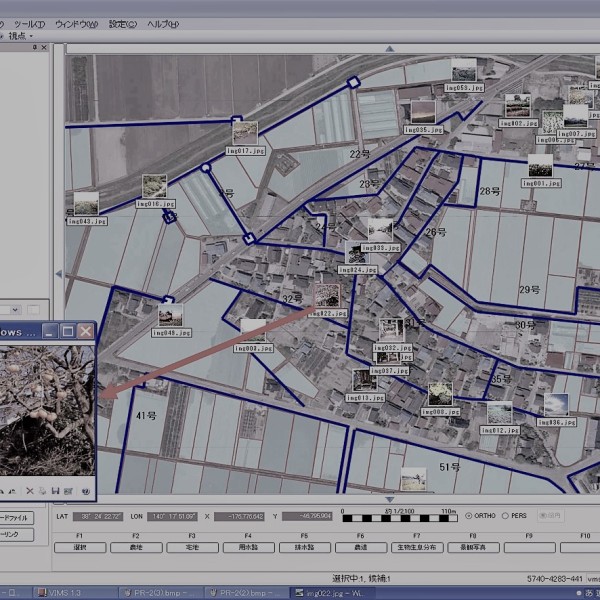
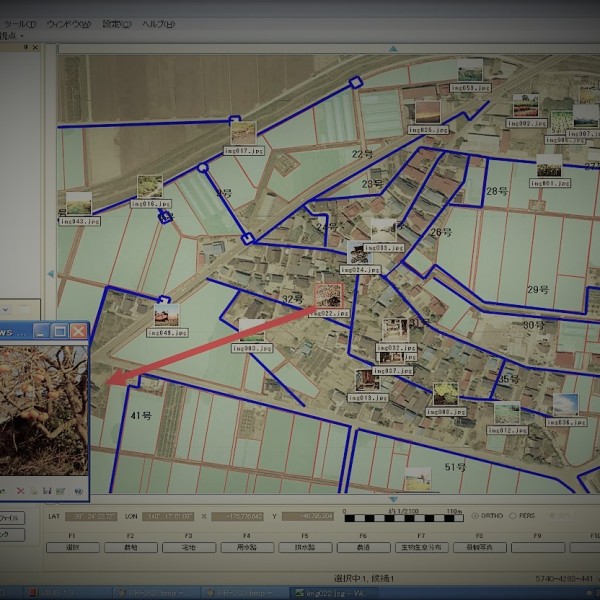
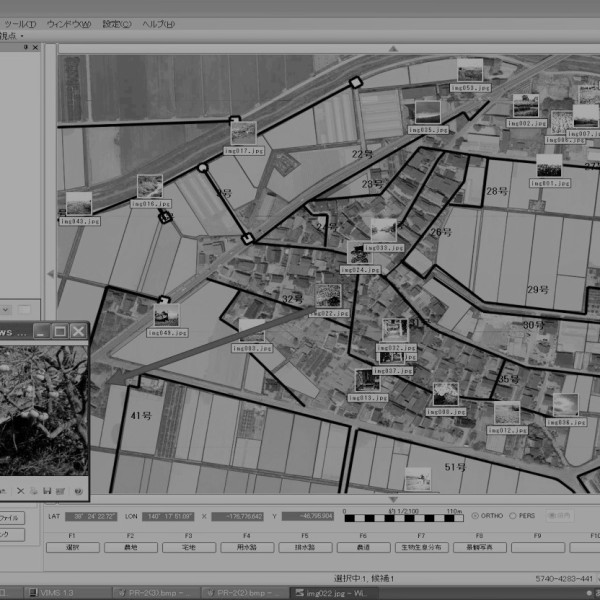








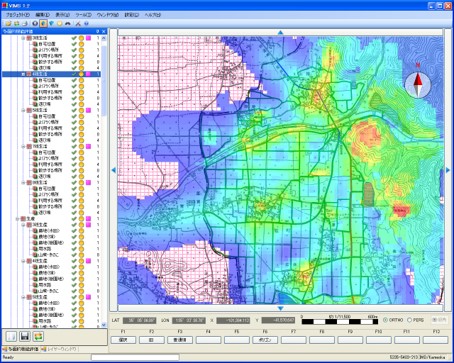
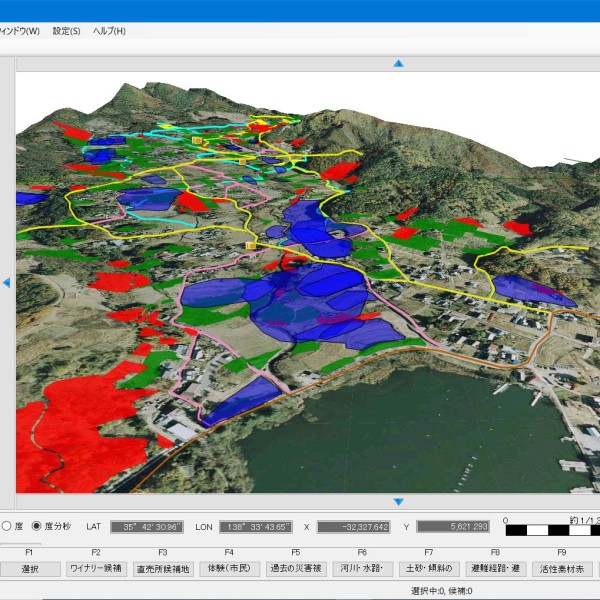
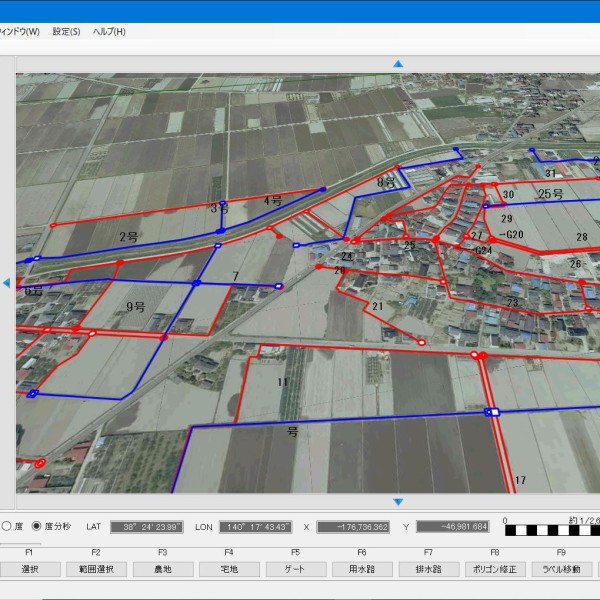


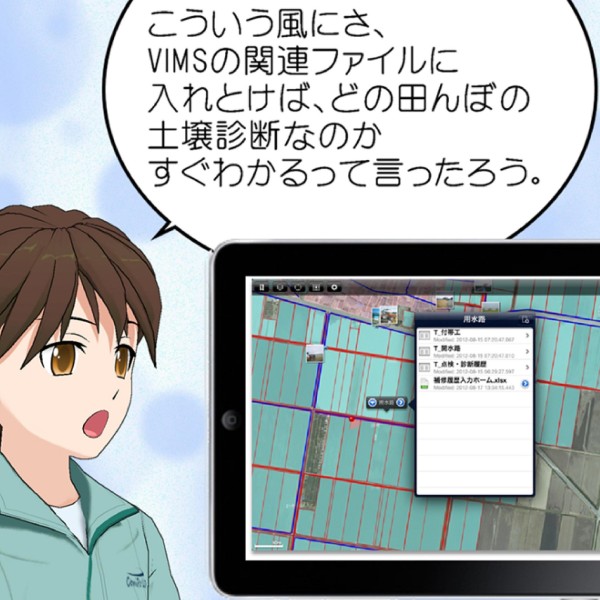

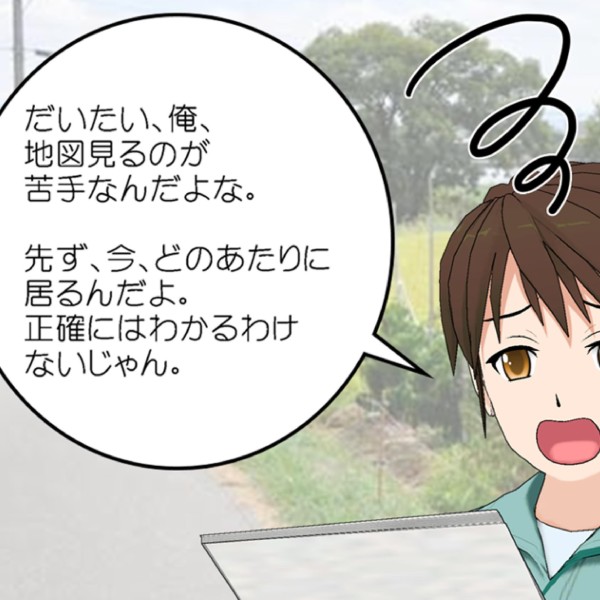



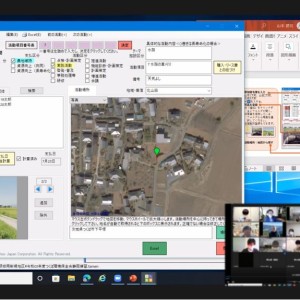

この記事へのコメントはありません。