
『青い壺』読んだ
有吉佐和子さんの『青い壺』を読みました。有吉佐和子さんは割と好きな作家で、高校から大学時代に『華岡青洲の妻』から初めて、『恍惚の人』、『紀の川』や『複合汚染』も読んだことがありますが、この『青い壺』は昭和52年、作家46歳の時の作品ですが、その頃にはちょっと飽きてたのかも知れない、読んでいなかったですね。
どうして最近この本が注目されているのかはよく分かりません。SNS的な短い物語の連続性を好む若者たちに受けいられたということなのか、現代の目まぐるしく変化する価値観とは対照的に青磁の壺の持つ美という価値が普遍であることに共感が得られたのだろうか、または、書籍販売のうまい戦略があってのことなのか。理由は様々あれ、2025年上半期のベストセラー文庫第1位となったようで、累計部数も50万部を超えたという。バカ売れなのです。
最近、私は娯楽ものばかり読んでいるし、目が悪くなってからは、なかなか本格的な文学作品が読めずにいます。映画やアニメばっかり見ていて、頭がかなり悪くなっているのでしょう。作品が言いたい真意がスキッと入ってこない。だからちょっと読み切るのに苦労しました。もともと文学的素養が無いというだけかもしれませんが、こういう文学作品から作者の真意を掴むことができなくなっている自分がとても悲しい。なんでも歳のせいにしてはならないが、どうも歳、やっぱり歳としたい。
『青い壺』は、青磁の壺が13編の様々な人々の人生の一断片に関わって連なっていくお話。その断片では、様々な社会的問題が浮き彫りになる。それによって生じる様々な人々の感情の絡みと機微の中を壺は転々と渡り歩くが、壺自体は普遍的な美を表しており、持ち主がどう変わっても、どんな位置に置かれても、どんな扱いを受けても、それらの人間の営みに翻弄されることは無く、凛として青磁の輝きを誰に主張するともなく発している。
人生の悲しみや喜びなどは、一つ一つはもしかしたら大した問題ではないのかもしれない。それは人生としてすべて大切な一面なのであって、いつでも形を変えずにそこに存在している人生そのものが美であるのです。人生の断片に捕らわれてはいけないと言っているように私には読めました。これは有吉佐和子さん40代の作品ですが、私の40代を振り返ると、とてもこうした境地には行きつかなかったように思います。あの頃は一所懸命、泣いて笑って、時には壺を壊すときもあり、がむしゃらに生き方を探っていたように思います。有吉さんのようなこんな達観した表現ができることに感動を覚えますし、この本を読んでいると、人生は何があっても、あたたかい人間の心を忘れてはいけない、それが自分の人生だからと教えてくれているように思えてならないのです。病気になっても、病気と言う別の生き方があるんじゃない。自分という本来の生き方の中に美が存在し、付き合ってくれる病気があるだけなんだと強く感じ、勇気を貰える気がします。
推理小説やバイオレンス、映画やアニメの動画ばかり見ないで、たまにはこういう文学作品にも触れておかないといけないなと思った次第です。
コメント ( 0 )
トラックバックは利用できません。
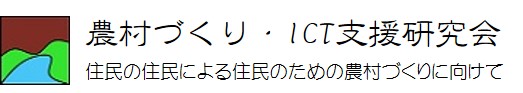









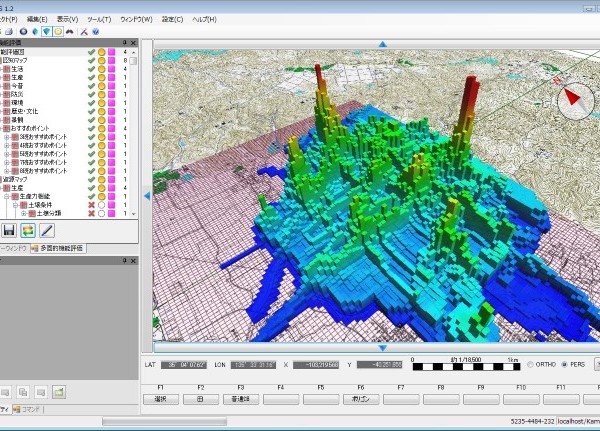










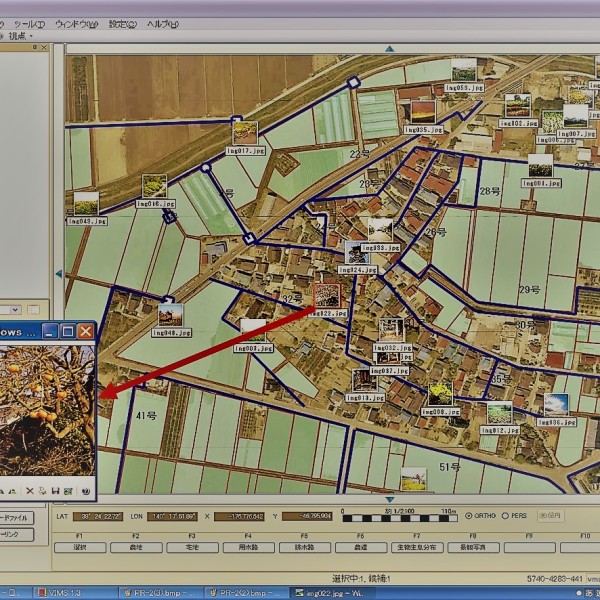
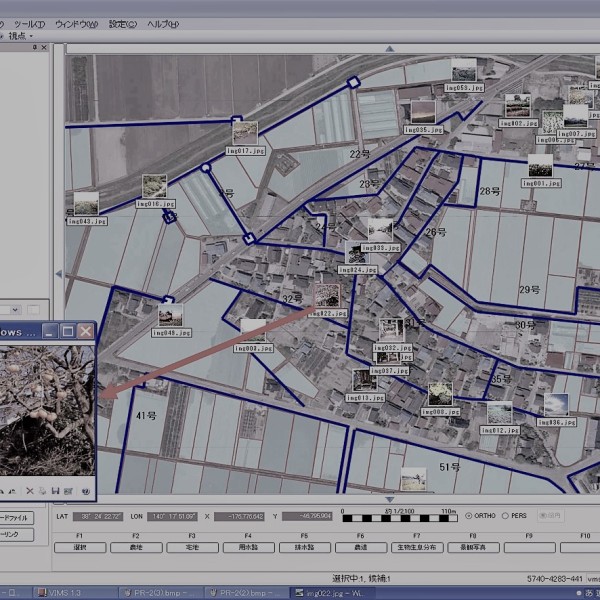
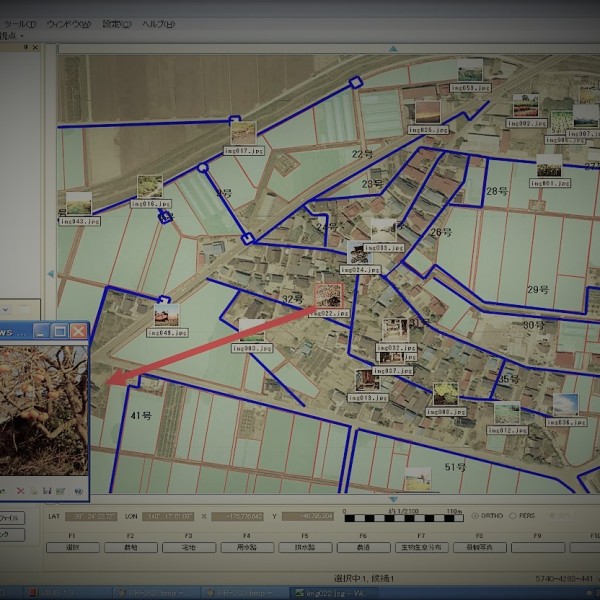
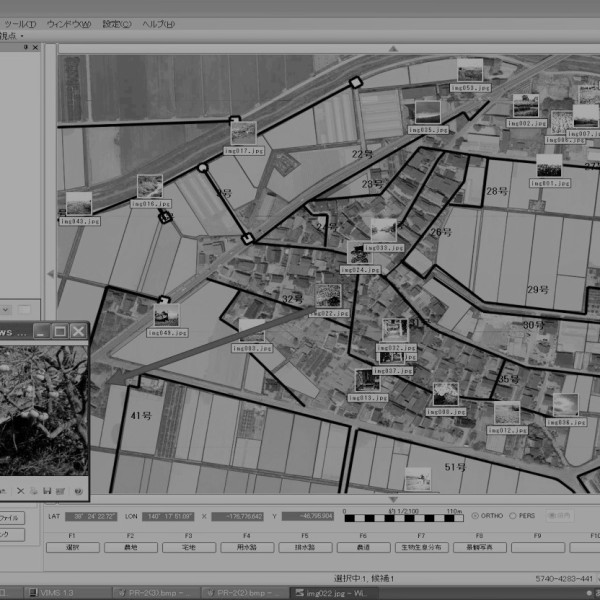








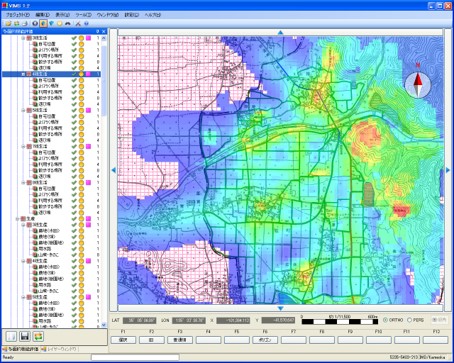
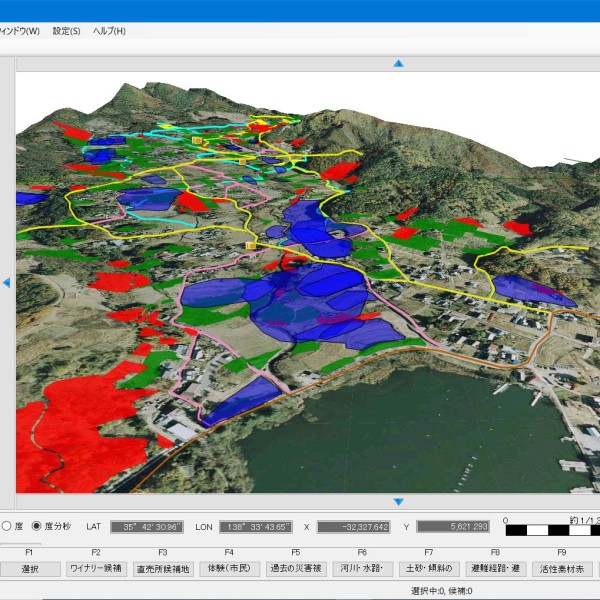
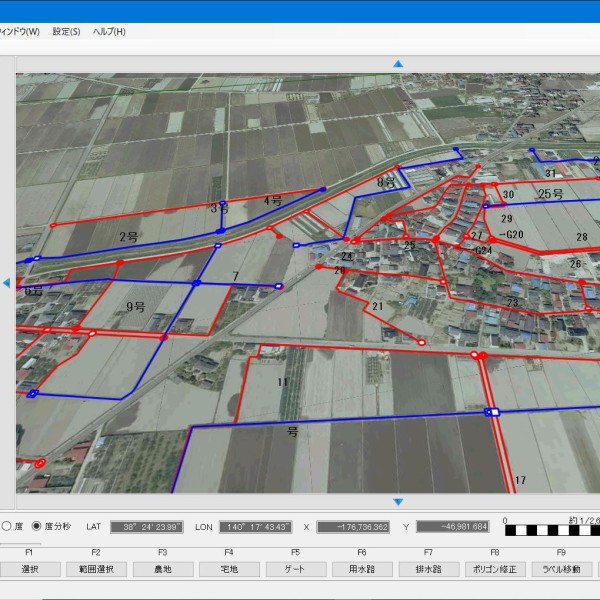


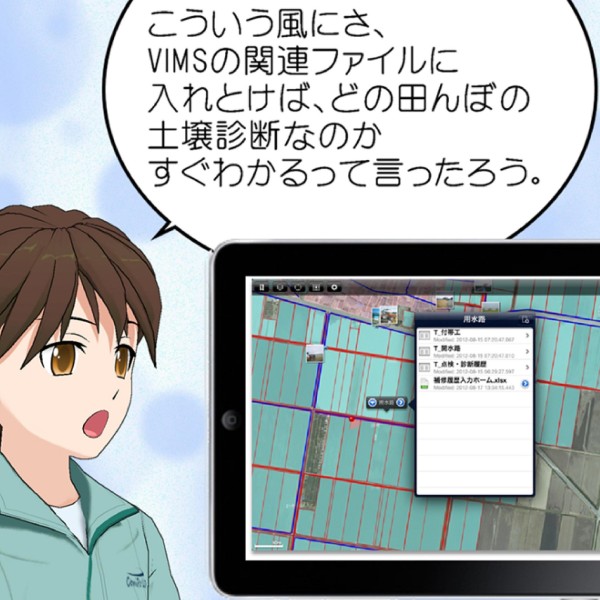

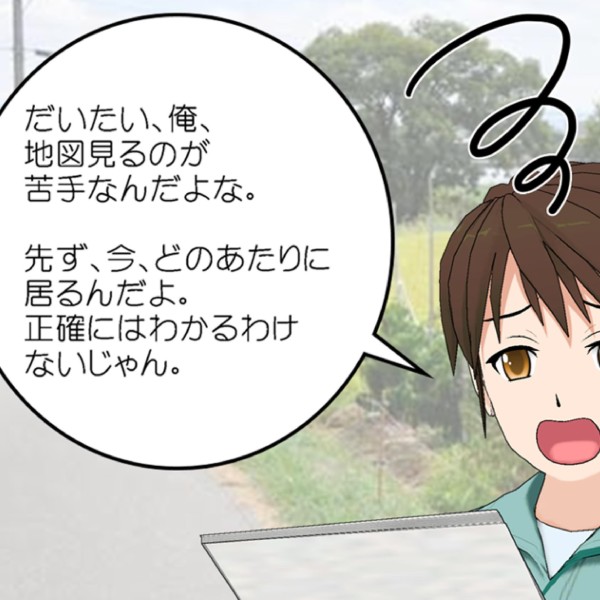





この記事へのコメントはありません。