
酒はやめられない
「酒は百薬の長」と言われますが、それに繋がる言葉は「されど万病の元」であり、ほどほどにしておくのが良いのでしょうが、酒好きの私としては、後の言葉は聞かなかったことにして、とりあえず好きなだけ飲んでいます。癌になってから少しは体調も気にしてはいますが、美味い地酒となると、どうしても飲みだすと止まりません。気持ち的にはこの辺で控えておこうと思うものの、口が御猪口を迎えに行ってしまうし、コップに酒が無くなると、勝手に一升瓶に手が伸びるのです。そして、息子に「おやじぃ、もう一杯飲むっ!」って言われるとニヤッとしてぐい吞みを差し出し、妻に「もうやめときないさいよ!」と言われてもニヤッとしてぐい吞みを差し出してしまいます。それくらい好きな訳です。
30代、40代の頃は、1晩で一升半ぐらい空けることもありましたが、今は、年のせいもあるのか大酒はできなくなり、多く飲むときでも精々2合ぐらいになりました。飲むことだけではなく、地酒の専門店などで全国の様々な酒を買って、土、日の夜に妻と二人で、息子たちがいる時は彼らも加わって、酒談義をしながら飲むことの方に、酒のみの楽しみが変わって来た感じです。
昔から酒を飲むとラベルをはがしてアルバムに貼って、コレクションしたりしていましたが、いつのまにか無くなってしまい、その後スマートフォンを持つようになった10年ほど前からは、飲んだらすぐに瓶の写真を撮ってコレクションするようになりました。獺祭、十四代、飛露喜、八海山、久保田、黒龍、栄光富士、鳳凰美田、田酒、鍋島と特に辛口・甘口、味や地域の拘りはなく、とにかくたくさん種類を飲むことにしていて、スマートフォンに溜まった写真枚数も先日300種類を超えました。
それだけたくさん飲んだのだから酒には詳しいし、唎酒もできるだろうと思われるかも知れませんが、実はそんなことはまったくありません。たくさんの種類を飲み過ぎて、今や何が美味いのか分からなくなってしまいました。酒の美味さよりも、家族で「このあいだ飲んだ奴の方が私は好き」とか「あの味と似ているね」とか、パケ買いの割に美味いだ、これはなかなか手に入らない奴だから心して飲めだと、互いに言いたいことを言い合って、家族品評会をしながら飲むことに酒飲みの幸せを感じます。
先日、会津へ旅行した時も、福島市内の有名な酒屋さんへ寄らしていただきました。日本屈指の酒造りを誇る会津だけのことはあり、いくつも名店はありますが、ちょっと変わったところで、ここでしか手に入らないオリジナルなお酒を売っている「小さな酒屋きしなみ酒店」さんで4本ほど買わせてもらいました。アイストップの写真でコラージュした「心静か」や「心ひとつ」というお酒は喜多方市の「会津錦」の蔵元さんで造ったもので、他ではなかなか手に入らないお酒だそうです。美味さもさることながら、その希少性と、お店の方の熱心な解説にも惚れこんで買って来たのですが、「心ひとつ」を空けたところで、私のスマホの酒写真コレクション300本目となりましたので、今回は記念の投稿をしてみました。
癌になっても酒はやめられないのですが、楽しみ方はいろいろと変わってきているようにも思います。農村づくりに欠かせない農村のお宝の魅力も、単に資源としての存在の魅力だけでなく、その楽しみ方を変えて行けばいくらでも違った魅力は出てくるものだと思います。今更ではありますが、酒飲みの楽しみ方を探すことは農村の魅力を探すことに通ずるものを感じます。

※この7本は特に私のお薦めの酒です。左から黒龍しずく(福井県)、十四代酒未来(山形県)、イットキ―(新潟県)、来福8%(茨城県)、Ohmine2grain(山口県)、豊香(長野県)、栄光富士GMF24(山形県)、それぞれに誕生日だとか記念日だとかの思い出があり、瓶の写真を見るとその頃のことを思い出します。
コメント ( 0 )
トラックバックは利用できません。
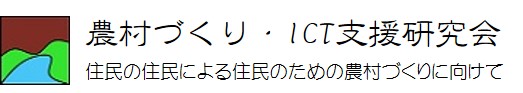









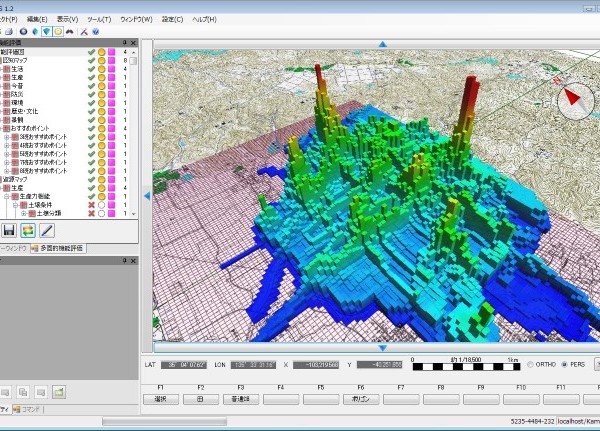










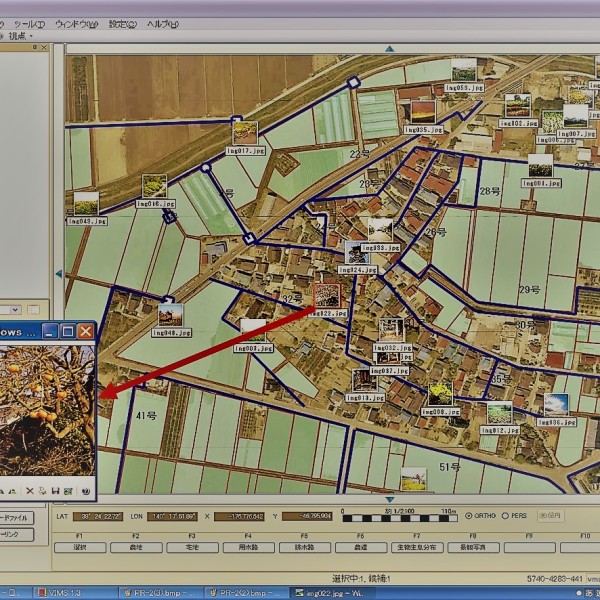
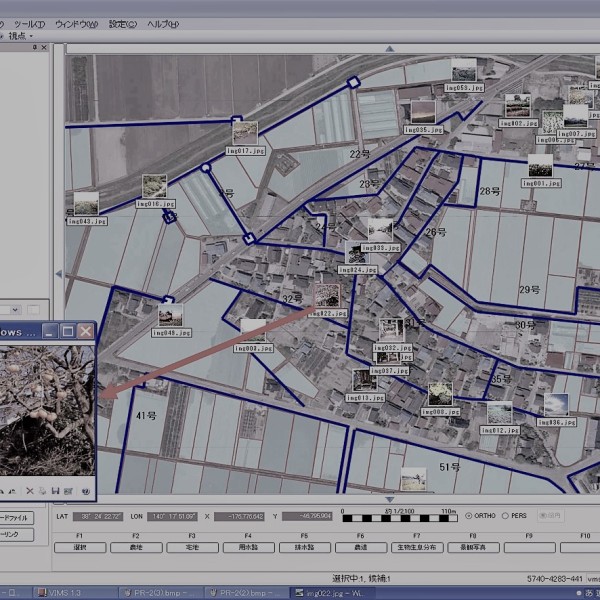
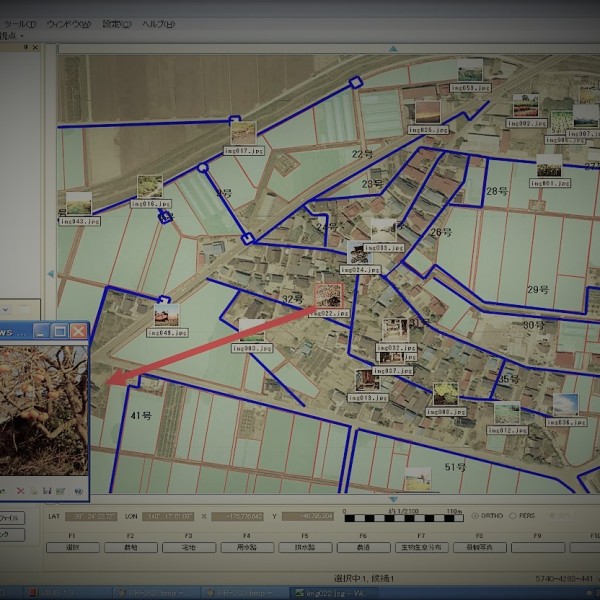
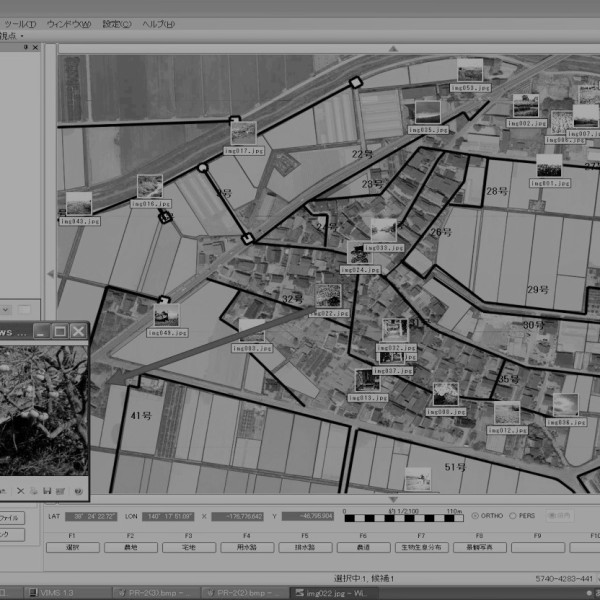








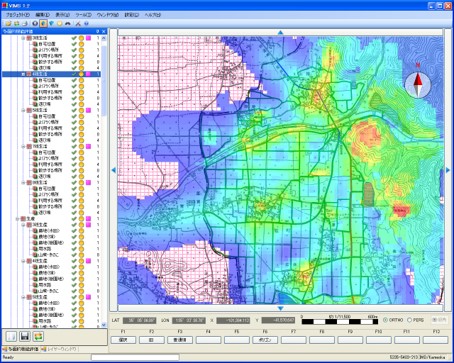
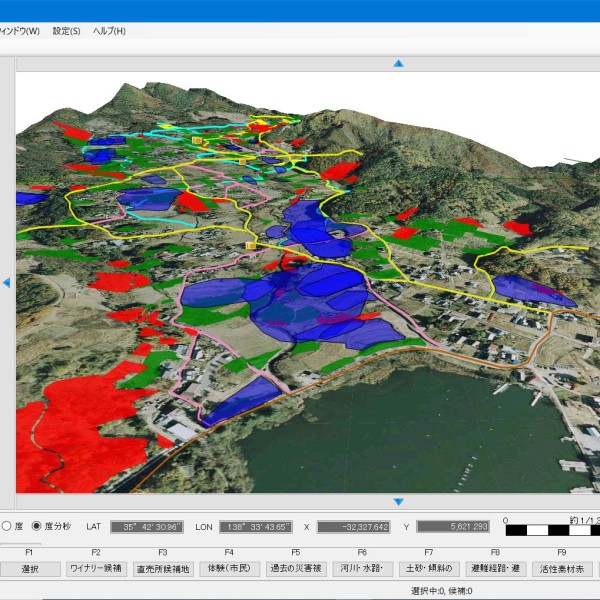
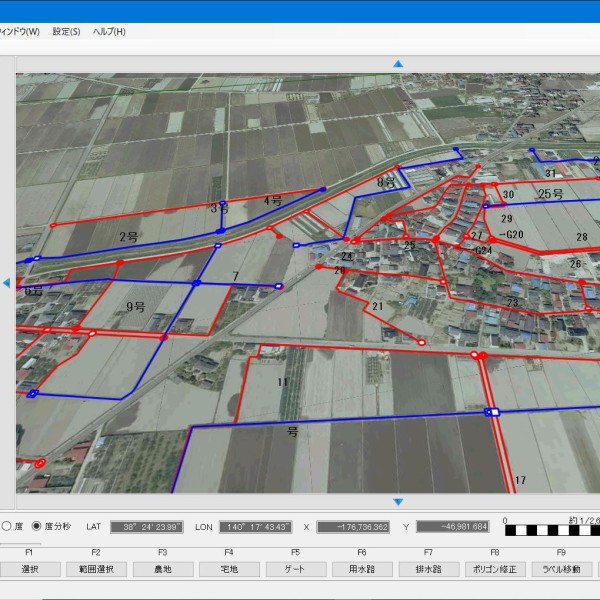


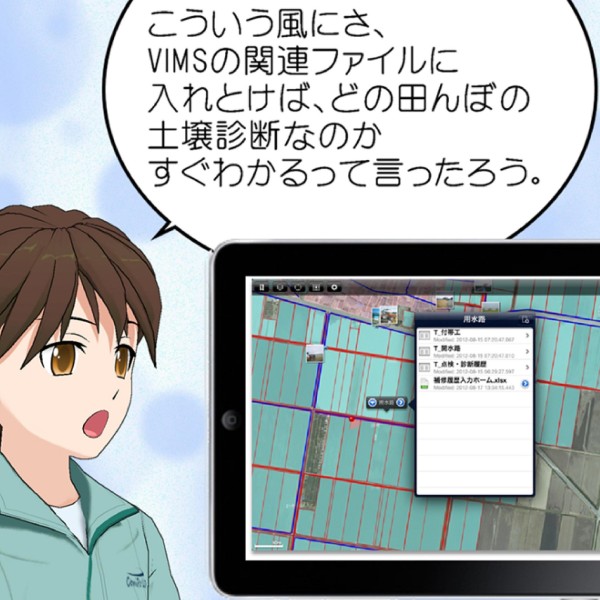

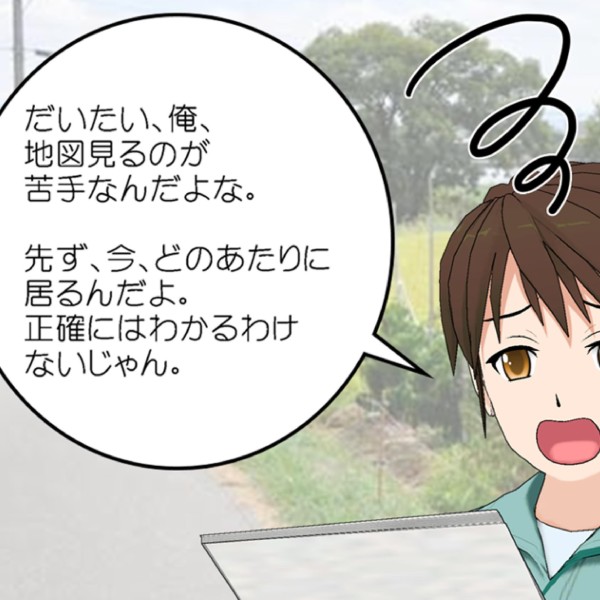





この記事へのコメントはありません。