
漬物の特派員
昔、ある集落の農村づくりであった話です。ワークショップやその後に開く懇親会の席で、いつも良い意見を言ってくれる若い女性がおられました。京都市内の百貨店で働いていたという京都市内出身の女性が、お嫁さんとして、山深い集落の農家に嫁いできたと言うことでした。若い女性と言っても、それは集落内では若いということであって、もうお子さんも二人いらっしゃって、30代後半だったと思います。子供会の行事などでは、積極的に参加し、子供の面倒見もとてもよかった。
集会では、なんか一言物を言わないと気が済まないようで、途中の議論で、しゃしゃり出て反対意見を述べるなんてことはなかったですが、議事進行役が、「最後に何かありますか」って聞いて、誰も意見が無いようだと、必ずと言って、「ちょっといいですか。感想みたいなことになるんですれど・・・」と、そろりと手を挙げ、前置きをつけながらしゃべり始めました。
普通、農村部では、若い人は大方は端っこの方に座っていて、話を振っても、「特に何もありません」という場合が多いのですが、この集落は、前から、若い人や女性がとても活発に意見を言う地区ではありました。
オリンピック組織委員会の森会長は、女性が話を始めると長い、控えろみたいなことを言っていましたが、この地区は、かなりじっくりと話を訊く集落柄があって、例え「感想」であっても、もしかしたらいい意見になるかもと、役員をはじめ、誰もが嫌な顔をしないで聞いていました。
この女性の話も、確かにどうでもいいような前口上に始まり、枕も結構長く、本題に行き着くまでに10分はかかりましたが、話は上手いし、ついつい耳を傾けてしまう。どうでもいいような話も、最終的には本題の前振りの前振りみたいなもので、決してどうでもいいともいえません。私は、4、5回ほどしかこの方の話を集会で聞いたことは無いのですが、区長さんによると、毎回何か話すから、最近は早めに議題の時間を切り上げて、最後のフリートーキングに時間を取って、彼女が喋りはじめるのを待っていると言う。意見を言う方もさることながら、利き手も大したものである。
さて、私が聞いたこの女性の話でひとつ面白いのを思い出したので、今日はそれを紹介したいと思います。
その集落では、京漬物の加工品を作って、毎年数回、京都の百貨店に出品していました。加工組合の女性陣が数名繰り出して、自ら作った漬物を宣伝も兼ねて売りに出る訳です。この仕組みも、この女性が百貨店で働いていたことを機に始まったと聞いていました。次々と活性化のアイデアが出るらしいのですが、彼女自身は積極的にアイデアを採用してもらおうというのではなく、自分なりに気づいたことで、変だなと思うこと、こうしたら面白いのにと思うことを、感想として述べているだけなのだが、それが次々と当たるみたいでした。
もう数回、百貨店での販促イベントが行われていて、この日の議題もその年の活動についての意見交換会だったのです。古い話ですので、すべてを覚えている訳ではないので、断片を引っ付けて、彼女が言った風に再現すると以下になります。
「うち、子供会の活動を手伝わせてもらってますんですけど、子供たちの発想って面白いなぁと思うことがよくあるんどすぅ。先日ね、『私のまちの未来』というテーマで絵画コンクールをやってみたんですぅ。ほんなら、子供たちの絵に、けっこう田んぼや畑が綺麗に描かれて、虫がいっぱい飛んでいたりするんですぅ。私、もっと新幹線が走ったり、高い駅ビルが建ったりするんかと思うとったら、そんなことあらへん。子供らの未来は、かなり自然の多い田園がそのまま残されるように描かれているんどすなぁ。これ、凄いことやと思わしまへんか。子供なりにこの地区の自然が好きなんやなぁと思うんです。なのに、就職する処がないよってに、結局は、高校出たら、大阪や京都に行ってしまうし、大学へ進学する子もみんな都会へ出てしまいますやろ。終いには『木綿のハンカチーフ』になってしまうんどすわ(『木綿のハンカチーフになってしまう』とは、太田裕美の歌詞のことを言っている。田舎から都会へ出た男の子が都会の色に染まってしまい、田舎に残した恋人を忘れ、帰ってこなくなる。田舎に残った女の子は、木綿のハンカチ―フで悲しみの涙をぬぐうというストーリー)」
ここで一息ついて、また喋り出す。
「うち、これおかしいと思うんどすぅ。都会に出て、数年で自分の故郷を捨てるなんて本当はできないのんとちゃい(違い)ますか。そりゃ鮮やかな都会の輝きに惑わされているだけで、結局、年取ったら、戻ってくる人も多いですよね。いつまでも育った土地に心は残っているんやあらへんかと思うんですぅ。いや、ほんならねぇ、都会にいる間も、この集落出て行った子らには、この集落といつも繋がっているんやということを思わせとかんとあかんのやないかなと思うんです。そんな忘れてしまうような魅力やないということを、いつも心の片隅に持っといて貰わんとあかんと思うんどすぅ」
ここまで話して、ようやく一番言いたいことに繋がっていくようだ。
「うちらの集落から都会に出た子らは、大学生も含め、みんなうちらの集落の特派員ということにして、漬物を百貨店で売るのも大事やけど、その子らに送って、その子らに近所の人やお世話になっている人に配ってもらって、一言「ぼくの生まれたとこで作ってる漬物ですわ」と言ってもらったらいいんちゃいますか」
田舎の漬物が特産として都会で売れることが『都市農村交流』ではなくて、地元出身の子供たちが都会へ出て、「これが私の故郷の漬物です」と胸を張れることの方が『都市農村交流』の価値としては高いと彼女は言うのだ。この意見にはおったまげた。でも、この女性の意見、実は、この後のサゲ(落ち)が素晴らしい。
「『木綿のハンカチーフ』には絶対したらあきまへんけど、そもそも、うちは自分の魅力で、都会へ行った男を絶対に故郷に帰らせますけどね」
地域住民、大爆笑である。
コメント ( 0 )
トラックバックは利用できません。
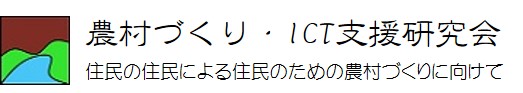









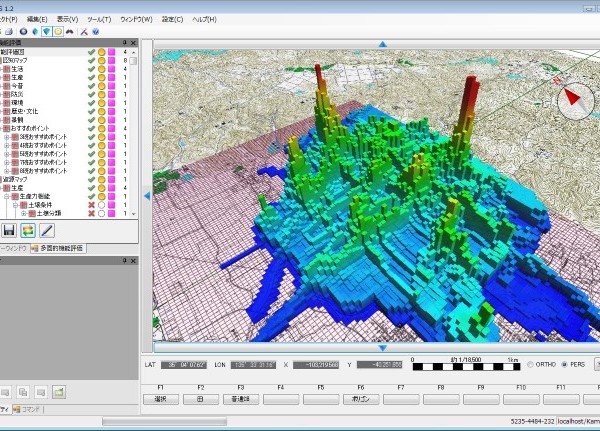










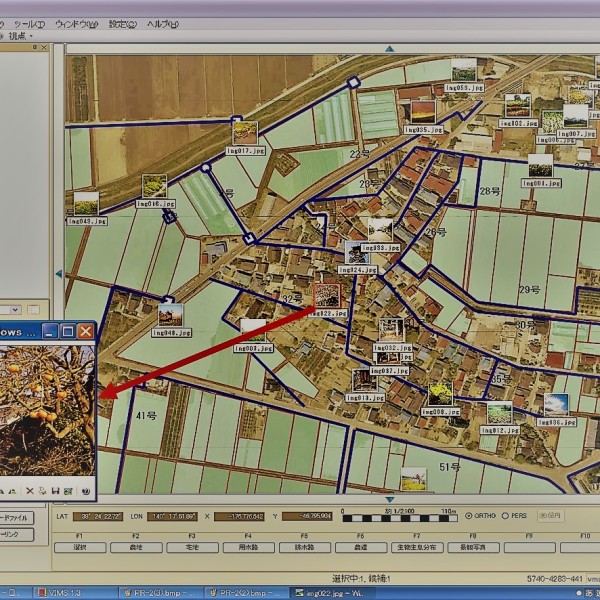
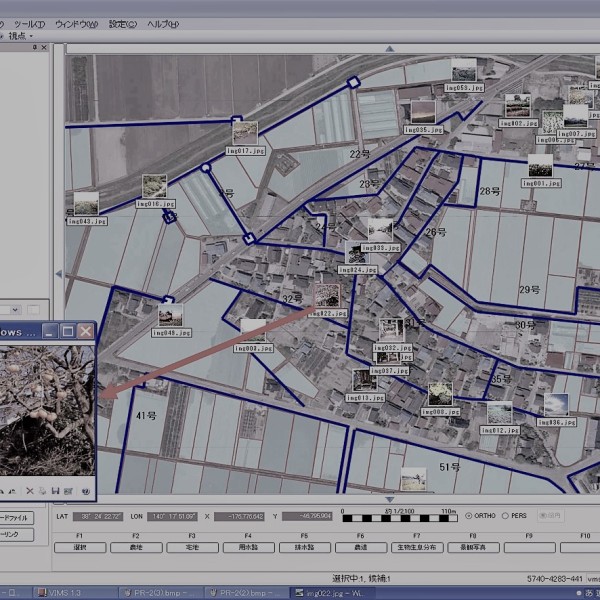
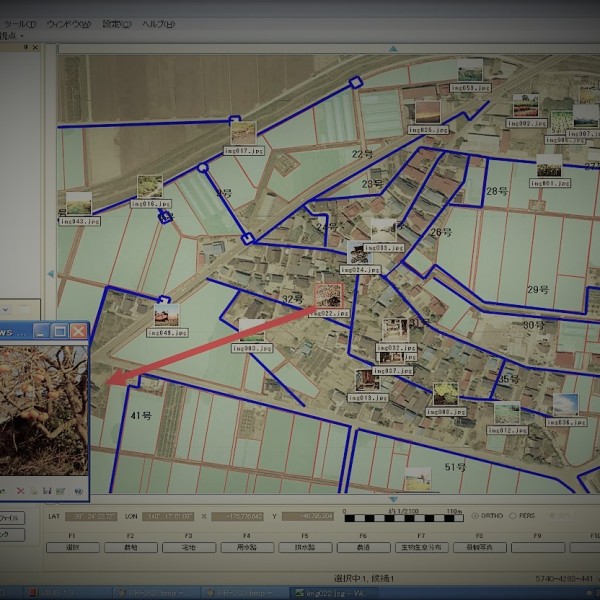
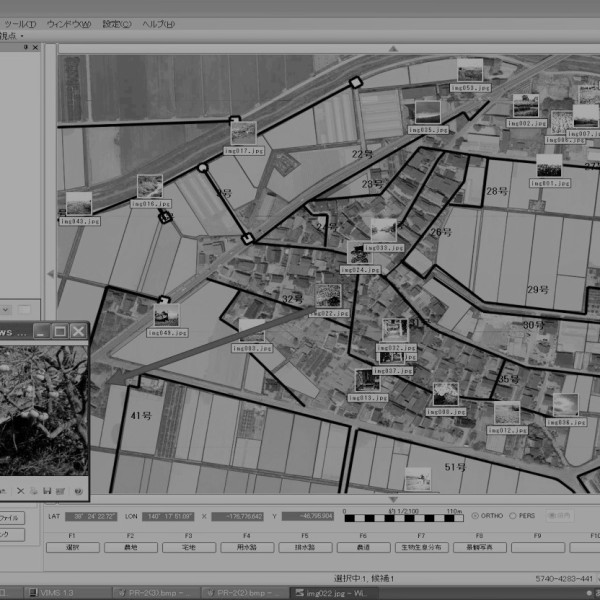








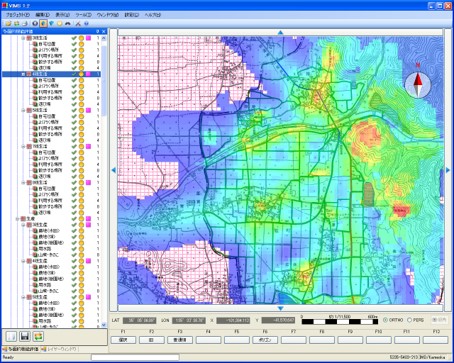
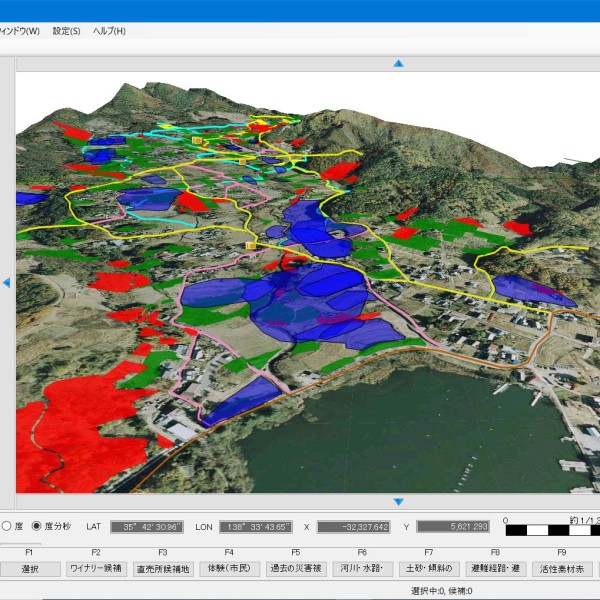
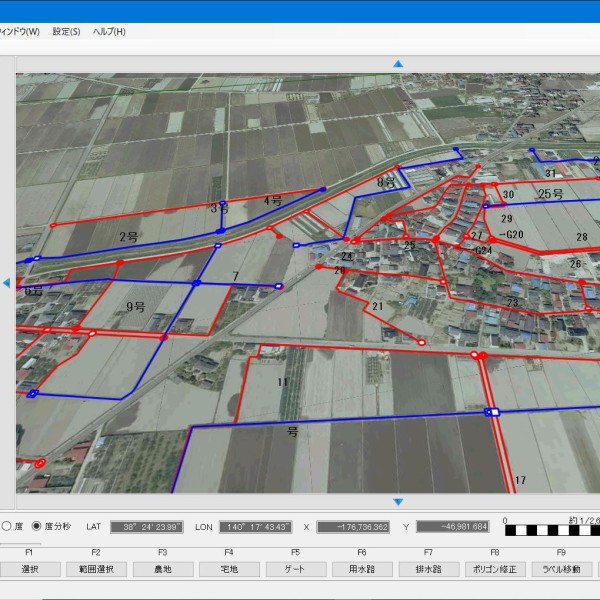










この記事へのコメントはありません。